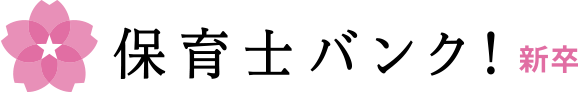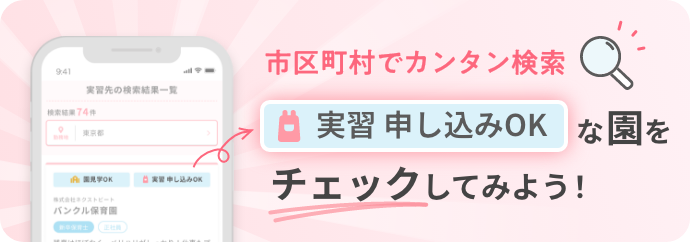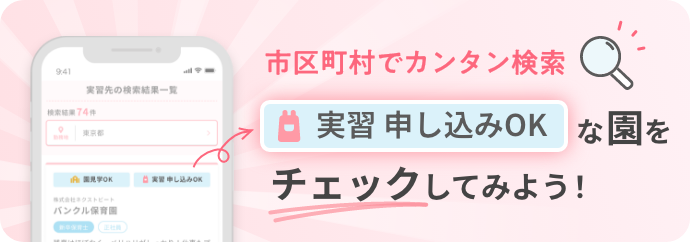乳児クラスの0・1・2歳児が楽しめるゲーム性のある室内遊びのアイデアをお届けします。宝探しや魚釣りゲームなど盛り上がるゲームを紹介!参観日などの親子レクレーションの中でも取り入れられるため、参考にしてみてくださいね。ゲーム性のある遊びを取り入れるねらいについても具体的にまとめました。
 ziggy / stock.adobe.com
ziggy / stock.adobe.com
0・1・2歳児クラスでゲーム性のある室内遊びを行なうねらい
保育園や幼稚園では、梅雨の雨の日や夏の暑い日、冬の寒い日などは室内遊びがメインになることでしょう。
乳児クラスを担当した際、ゲーム性のある室内遊びを取り入れたいと考える保育士さんもいるのではないでしょうか。
まずは、乳児クラスで室内遊びを行なうねらいについて、下記で0歳児・1歳児・2歳児の年齢別に見ていきます。
| 0歳児のねらい | ・手足や指を動かすことを楽しむ ・保育者とのふれあいや遊びを通して五感を育む |
| 1歳児のねらい | ・歩く、走る、投げるなど、のびのびと全身を動かす ・保育者とのやり取りを通してゲーム遊びを楽しむ |
| 2歳児のねらい | ・友だちといっしょに遊ぶ楽しさを味わう ・保育者や友だちと言葉のやり取りを楽しむ |
年齢ごとに子どもが楽しめる活動は異なるので、クラスの子どもたちの興味やできることにあわせてゲーム遊びを取り入れられるとよいですね。
乳児クラスの室内遊びのねらいがわかったところで、どんなゲーム遊びを取り入れるとよいのかくわしく見ていきましょう。
0歳児・1歳児・2歳児と年齢別にゲーム性のある室内遊びのアイデアを紹介します。
ルールが簡単なゲームが多いので、参観日などで親子レクレーションにも取り入れてみてくださいね。
【乳児向け室内遊び】ゲーム性のある遊び:0歳児
 Paylessimages / stock.adobe.com
Paylessimages / stock.adobe.com
まずは、0歳児向けのゲーム性のある室内遊びを見ていきましょう。
風船集めゲーム
0歳児はさまざまな物にふれて、感触や特徴を楽しめる頃かもしれません。
風船を使ったゲームを取り入れてみてはいかがでしょうか。
用意するもの
- 風船 数個
- 新聞紙 適量
- 段ボール 1個
- ビニールプール
遊び方
- ビニールプールのなかに新聞紙を破って敷き詰めます。
- 風船を(1)の中に入れます。
- 段ボールを組み立て、箱の形に仕上げます。
- ビニールプールの中に子どもを誘導し、(3)の中に風船を集めます。
遊びや援助のポイント
このゲームでは、敷き詰めた新聞紙の感触を味わいながら風船を集める遊びを行ないます。
事前準備として、ビニールプールを用意することになります。
もしビニールプールが用意できなかったときは、床に新聞紙を敷いて行なうことも可能です。
0歳児の赤ちゃんがけがをしないように広いスペースを確保したり、寝転びやすいようにマットを敷いたりして安全に配慮して行ないましょう。
床で行なう場合は、ビニールプールのように仕切りとなるものがないので、ビニールテープやカラーコンを用いて範囲を決め、自分の目が届くなかで行なうとよさそうです。
ハイハイゲーム
ゲーム性のある室内遊びのアイデアとして、ダンボール製のトンネルを使ったハイハイゲームを紹介します。
用意するもの
- 段ボール 3~4個
- テープ
- カッター
遊び方
- つぶした状態のダンボールを並べ、取れないようにテープで固定します。
- (1)を切り抜いて窓を作ったり、周りを装飾したりします。
- (1)を組み立て、トンネルの形に仕上げます。 スタートする位置を決め、(3)をハイハイでくぐり抜けるよう促します。
遊びや援助のポイント
身体を動かして遊ぶことができるため、戸外に出られない雨の日や夏の暑い日にぴったりなゲームです。
ダンボールの中は意外と薄暗いため、側面に窓を作って中を明るくすると、0歳児の赤ちゃんも周囲にいる人や景色が見られるようになりますよ。
また、0歳児の赤ちゃんの中には、窓を作ってもダンボールの中が怖いと思う子が出てくるかもしれません。
ハイハイで進みやすくするために、保育士さんはゴール付近で音のなるおもちゃを鳴らしたり、赤ちゃんの名前を呼んだりすると興味をもって進んでくれそうです。
PEテープですもうゲーム
PEテープを活用して引っ張り合いゲームをしてみましょう。
用意するもの
- PEテープ
遊び方
- 子どもに座った状態で、PEテープの端を持つように促します。
- 保育士さんは(1)と反対側の端を持って座ります。
- PEテープで子どもと引っ張り合いをします。
遊びや援助のポイント
この室内遊びではPEテープを工夫することで、子どもたちがさらに盛り上がるかもしれません。
例えば、テープの真ん中にポンポンをつければ、引っ張りあう度に揺れる動きを楽しむことができるでしょう。
また、鈴など音が鳴るものをテープに結びつけると、引っ張り合うことで音が鳴るため五感が刺激されそうです。
このように、言葉での意思疎通をはかるのが難しい0歳児の赤ちゃんには、保育士さんが積極的に話しかけたり、肌と肌をふれ合わせたりしてスキンシップをとることが大切と言えるでしょう。
なお、親子レクレーションとして取り入れるときは、保護者の方と子どもが向かい合わせになり、PEテープの引っ張り合いをして楽しんでもらいましょう。
カード引っ張りゲーム
0歳児の赤ちゃんがカードを引っ張る感覚を楽しめるゲームを紹介します。
用意するもの
- ひも 1本
- 洗濯ばさみ 1個
- ラミネート機
- ラミネートフィルム
- 画用紙 1枚
- 好きな色のペン
- はさみ
遊び方
- 画用紙に好きな絵をかき、ラミネート加工をしてカードを作ります。
- ひもに洗濯ばさみを結びつけ、(1)のカードをはさみます。
- (2)を保育士さんが持ち、子どもがカードを引っ張れるように促します。
遊びや援助のポイント
ロープの高さは、子どもがカードに手を伸ばしたら届く程度に調整しましょう。
歩くことができる子どもとまだハイハイの子どもがクラスに混在している場合は、高さの違うロープを用意してコーナーを分けておくとよいかもしれません。
また、カードは市販のものでもよいですが、親子レクレーションで取り入れるときはあらかじめ保護者の方に描いてもらったカードを集め、ラミネート加工して使うこともできます。
春はいちごの絵を用意していちご狩り、冬はみかんの絵をぶらさげてみかん狩りなど季節に合わせて楽しむことができそうですね。
鈴鳴らしゲーム
0歳児の赤ちゃんが、鈴を鳴らして楽しめる机上遊びを紹介します。
用意するもの
- 空き箱 1個
- 鈴 2個
- ひも 1本
- キリ
遊び方
- 空き箱の側面に穴を開けます。
- (1)のちょうど反対側にも再度穴を開けます。
- (1)(2)の穴にひもを通します。
- ひもの両端に鈴を結びつけます。
- (4)のひもを引っ張り、鈴の音を鳴らして遊びます。
遊びや援助のポイント
穴は2カ所だけでなく、他にも開けてひもを通せばさらにおもしろい遊びになりそうです。
さまざまな大きさの鈴を用意すれば、ひもを引っ張るたびに変わる音を楽しむことができるでしょう。
また、空き箱はお菓子の箱や牛乳パックなど、身のまわりのものを使うとよさそうです。
0歳児の赤ちゃんが扱っても壊れにくいように、できるだけ厚くて丈夫な箱を選ぶとよいかもしれませんね。
関連動画:【3分で完成!!】ひものおもちゃ【0歳児向き】/保育士就活バンク!
ティッシュ引っ張りゲーム
子どもが夢中になって遊べる、ティッシュ引っ張りゲームについて見ていきます。
用意するもの
- ティッシュの空き箱 1箱
- ガーゼ 8枚
- ビニールテープ
- キリ
遊び方
- ティッシュにガーゼを入れます。
- 箱からガーゼを引っ張り出す動作を楽しみます
遊びや援助のポイント
0歳児の赤ちゃんがティッシュを無限に引っ張って遊べる、机上遊びのアイデアです。
白色のガーゼだけでなく赤色や青色の布なども混ぜれば、見て楽しむこともできるでしょう。
また、子どもがすぐに遊び終わってしまう場合は、ガーゼの枚数を増やしてみてもよさそうです。(詳しい作り方はこちら)
【乳児向け室内遊び】ゲーム性のある遊び:1歳児
ここでは、梅雨の時期や雨の日、夏の暑い日などに1歳児クラスで楽しめる、ゲーム性のある室内遊びを見ていきましょう。
手遊びゲーム
手遊び歌の「かみなりどんがやってきた」を使った準備いらずのゲームを紹介します。
遊び方
- 歌に合わせて身体を動かします。
- 歌に合わせて身体さまざまな部位を隠します。
遊びや援助のポイント
「かみなりどんがやってきた」は、かみなりどんにおへそや頭を取られないように、手で身体を隠す手遊び歌です。
雨の日や雷が鳴っているときに行えばより盛り上がる、梅雨や夏の日にぴったりなゲームでしょう。
動画では隠す場所が少しずつ増えていきますが、1歳児の子どもたちと楽しむときには1箇所から2箇所を目安に隠すとよいかもしれません。
事前に保育士さんがかみなりどんのペープサートを作り、子どもたちに見せながら説明すると、子どもたちは遊びをイメージしやすくなるでしょう。
保育参観や親子ふれあい遊びの際には、レクリエーションの一つとして楽しむこともできそうですね。
魚釣りゲーム
身近にある素材を活用して作ることができる、机上遊びを紹介します。
用意するもの
<魚>
- おもちゃのカプセル 1個
- クリップ 1個
- カラーフィルム 1枚
- 好きな色の画用紙 数枚
- PEテープ
- 目玉シール 数枚
- テープ
<タコ>
- トイレットペーパーの芯 1個
- 赤色の折り紙 1枚
- クリップ 1個
- 鉛筆
- テープ
- はさみ
<釣り道具>
- 画用紙 1枚
- タコ糸
- 割り箸 1本
- 磁石 1個
- ペン
- テープ
- はさみ
遊び方
- 魚釣りの道具を配ります。
- 魚釣りを楽しみます。
遊びや援助のポイント
このゲームで使用する釣り道具のタコ糸は、糸が長いとクリップに磁石を近づけて釣りあげるのが難しくなってしまいます。
1歳児の子どもたちがたくさん釣って遊べるように、釣り道具の糸は短めにするとよいでしょう。
また、青いビニールシートや画用紙を床に敷き、そのうえに魚を置くと本物らしくなって盛り上がりやすくなりそうです。
赤い魚を用意して金魚釣りゲームとして遊ぶこともできます。親子レクレーションの一環として楽しむのもよいかもしれませんね。(詳しい作り方はこちら)
ボーリングゲーム
1歳児の子どもたちがボールを転がして遊ぶ、ボーリングゲームを紹介します。
用意するもの
- 紙コップ 2個
- ビー玉 適量
- 好きな色の画用紙 数枚
- 新聞紙 1枚
- ビニールテープ
遊び方
- ボーリングピンに見立てた紙コップを並べます。
- (1)めがけてボールを投げます。
遊びや援助のポイント
1歳児クラスでボーリングゲームを取り入れるときは、ピンを倒れやすくするため、なかに入れるビー玉の量を調整して作るのがポイントです。
紙コップ以外にもペットボトルをピンにすることができますが、ビー玉の量が多すぎると重みで安定しやすくなり、ボールが当たっても倒れにくくなってしまいます。
保育士さんが一度ボールを当てて倒れやすさを確認するなどして、中に入れるビー玉の数を決めてみてくださいね。
また、ゲームの説明時に、保育士さんが一度ボールを転がしてピンを倒すところを見せると、子どもたちがどのようなゲームなのかを理解しやすくなりそうです。(詳しい作り方はこちら)
玉入れゲーム
1歳児の子どもたちといっしょに玉入れゲームをしてみましょう。
用意するもの
- 新聞紙 数枚
- 大きめのかご 1個
遊び方
- 新聞紙を丸めて、ボールをいくつか作ります。
- 玉を投げるスタート地点を決めます。
- (2)の場所まで子どもたちを誘導し、(1)を配ります。
- 保育士さんは玉を入れやすそうな場所に立ち、かごを持ちます。 子どもたちはかごを目掛けて(1)を投げます。
遊びや援助のポイント
実際にゲームを行なうときは、玉を入れやすいように口が開いているほうを子どもたちに向けて行なうとよいでしょう。
最初は低い位置から行ない、慣れてきたら徐々に位置を高くしていくと、その高さをねらって子どもたちがボールを投げる姿が見られるかもしれません。
このように、1歳児の子どもたちはものを掴んで投げたり、自由に歩き回ったりする姿が見られるため、その特徴を活かして親子レクレーションのゲームとしても取り入れるとよいですね。
宝探しゲーム
1歳児の子どもたちといっしょに、部屋の中に隠されたものを探す宝探しを楽しんでみましょう。
用意するもの
- 宝物(ぬいぐるみ・ボールなど) 数個
- バケツ 数個
遊び方
- 子どもたちに宝物を見せ、目をつぶるように促します。
- 保育室内に宝物を置き、上からバケツをかぶせて隠します。
- 隠し終わったら子どもたちに声をかけ、宝物を探すように誘います。
一斉に子どもたちが走り出すと、子ども同士でぶつかってけがをする恐れがあるので、ゲームが始まる前に「歩いて探そうね」など一言声をかけるとよいでしょう。
遊びや援助のポイント
バケツの代わりに箱やミルク缶などを使って隠すこともできます。
1歳児の子どもたちが持ち上げやすいよう、軽くてサイズの小さめなものにするとよいでしょう。
子どもたちが隠した宝ものを見つけられずに迷っているときは、状況を見て保育士さんが少しずつヒントを出していきます。
また、ゲームをするときは子どもたちそれぞれが宝物を見つけたうれしさを感じられるよう、複数個の宝物を隠しておくようにしましょう。
輪投げゲーム
1歳児の子どもが、紙皿を投げて遊べる輪投げゲームを紹介します。
用意するもの
- 紙皿 1枚
- 紙コップ 1個
- 段ボール 1枚
- 画用紙 1枚
- 鈴 1個
- のり
- テープ
- 好きな色のペン
- コンパス
- はさみ
遊び方
- ライオンを描いた絵を床に置きます。
- (1)めがけて輪に見立てた紙皿を投げます。
遊びや援助のポイント
ライオンだけでなく、うさぎやクマなど好きな動物をいくつか作るとさらに盛り上がりそうです。
紙皿も笑った目をかくなど何種類か作れば、動物の表情が変わっておもしろいでしょう。
また、うまく紙皿を投げられない子どもがいるときは、保育士さんが手を添えていっしょに投げるようにするとよいかもしれません。
なかなか輪が入らないときは、距離を調節するなどして難易度を変えてみるとよさそうです。(詳しい作り方はこちら)
詳しくはこちら乳児クラスの室内遊びで行えるゲームのアイデア:2歳児
ここでは、2歳児向けにゲーム性のある室内遊びを紹介します。
もの当てゲーム(再生時間:0:00~0:26)
新聞紙の穴から色々なものを見せて、子どもたちに当てっこゲームをしてもらいましょう。
用意するもの
- 新聞紙 1枚
- ぬいぐるみやおもちゃ 数個
- はさみ
遊び方
- 新聞紙の後ろにクイズの答えを隠しておきます。
- 「なにがかくれているかな?」と子どもたちに問いかけます。
- 答えが出そろったら正解を言います。
遊びや援助のポイント
子どもたちが当てるものは見えないように、紙袋などに入れておきましょう。
取り出すときは新聞紙を片手で持ちながら行なうか、保育士さん同士ペアになって行なうとスムーズにできるかもしれません。
また、イラストをかくのが得意な保育士さんは、穴の間から自分のかいた絵を見せるというアレンジ方法もあります。
一見お花に見えるけれど実はライオンでした、というようなひっかけ問題を何問か作ってみると、2歳児の子どもたちはよろこんでくれるかもしれませんね。
イラストを書くときは、色や形がはっきりわかるように大きく書くようにしましょう。
親子レクレーションで取り入れるときは保護者の方といっしょに答えを考えてもらえるとよいですね。(詳しい作り方はこちら)
グーチョキパーゲーム
雨の日でも身体を動かせる室内遊びとして、じゃんけんゲームを紹介します。
遊び方
基本的な遊び方は一般的なじゃんけんと同じです。
- 「じゃんけんぽん」という合図に合わせて、グー・チョキ・パーのそれぞれのポーズを子どもたちに取ってもらいます。
- じゃんけんを繰り返して身体を動かすことを楽しみます。
以下は、ポーズの一例です。
- グー:その場にしゃがみ込んで体を小さく丸める
- チョキ:手と足を前後に広げる
- パー:手と足を大きく横に広げる
遊びや援助のポイント
ポーズは2歳児の子どもたちとアイデアを出し合いながら、アレンジを加えてみてもよいでしょう。
保育士さん対子どもたちでじゃんけんゲームを行ない、全身を使って遊ぶことを楽しんでもらえるとよいですね。
やり方に慣れてきたら、最後の一人になるまでじゃんけん大会をすると盛り上がるかもしれません。
じゃんけん大会をするときは負けたら座ってもらうようにあらかじめ話をしておくと、誰が残っているのか分かりやすくなるでしょう。
また、子どもたちがじゃんけんのポーズに慣れてきたら、わざと「ぽん」と言うときに少し間を持たせると、いつ動きだすのか分からないため集中して遊んでくれるかもしれません。親子レクリエーションなどに取り入れると、盛り上がりそうです。
色探しゲーム
保育室の中から指定した色を探してもらう、色探しゲームについて紹介します。
色の名前が一致し始める2歳児頃にぴったりな遊びです。
遊び方
- 「〇色のものはどこにあるかな?」と、保育士さんが子どもたちに声かけします。
- 子どもたちに色を探してもらいます。
遊びや援助のポイント
子どもたちが〇色のものを見つけられるように促します。保育士さんは「色は歩いて探そうね」と、最初に子どもたちに伝えておくとよさそうです。
例題として挙げる色は、保育士さんの洋服やエプロンの色にすると子どもたちがすぐに見つけられるだけでなく、ふれ合いのきっかけにもなるでしょう。
また、色探しゲームでは広いホールや保育室全体を使って行なったり、一箇所に集まってその場を動かずに行ったりすることができます。
ホール・保育室内で行なうときは子どもが転んだりつまずいたりしないように、床にものが落ちていないかを確認してから行なうことが大切です。
一方、子どもたちに部屋の一角に集まってもらう場合は、動き回らなくてもできるように、子どもたちの目の前に色のついたおもちゃなどを置いておくようにしましょう。
ジェスチャーゲーム
レクリエーションとして親しまれる、ジェスチャーゲームの遊び方について説明します。
遊び方
- ジェスチャーゲームのお題を用意します。
- 保育士さんは子どもたちの前に立ち、動きだけでお題を表現します。
- 子どもたちに「なんの真似かな?」と聞いて答えてもらいます。
遊びや援助のポイント
乳児クラスでジェスチャーゲームを行なうときは、わかりやすいよう大げさな動作で行なうのがポイントです。
初めは動きだけで子どもたちに考えてもらい、答えがあまり出てこないときは、正解となるものの特徴を声に出すと当てやすくなるでしょう。
ルールが分かってきたら、子どもたちを出題者にして保育士さんが答えるのもよいかもしれませんね。
イス取りゲーム
室内遊びで楽しめる、イス取りゲームをやってみましょう。
用意するもの
- イス 人数分
- CD
- CDプレーヤー
遊び方
- 人数分の椅子を円形に並べます。
- 音楽に合わせて、イスの周りを時計回りに歩きます。
- 音楽がストップしたタイミングで、目の前にあるイスに座ります。 (2)(3)を繰り返します。
遊びや援助のポイント
定番のレクリエーションとして親しまれるイス取りゲームですが、2歳児クラスで行なうときはイスを減らすのではなく、人数分用意することがポイントと言えます。
何回か実施したことがあり子どもが遊び方に慣れている場合は、通常のルールのようにイスを一つずつ減らしていってもよいかもしれません。
その際は、避けた椅子を「応援席」として活用すれば、負けてしまった子どもも友だちの様子を見て楽しめるでしょう。
ボール集めゲーム
箱の色と同じ色のボールを集めるゲームを室内遊びに取り入れましょう。
用意するもの
- 好きな色のボール 適量
- 段ボール 数個
- ボールと同色の画用紙 各数枚
- のり
遊び方
- 段ボールを組み立て、周りに同色の画用紙を貼りつけます。
- ボールの色と同じ色の箱を用意します。(ボールが赤・青・黄の場合は、箱も赤・青・黄を用意)
- ボールを床全体に転がします。
- ボールを集め、ボールと同じ色の箱に入れて遊びます。
遊びや援助のポイント
箱の色は子どもたちが判断しやすいよう、画用紙やカラーガムテープなどで飾り付けるとよいでしょう。
また、ボールを拾いに行くときは歩いて移動するように、あらかじめ約束を伝えることもポイントです。
親子レクレーションで取り入れるときは、子ども同士でぶつからないように、広いスペースを確保して行なうことが大切です。
0・1・2歳児クラスでゲーム性のある遊びを取り入れて楽しもう!
今回は、0歳児・1歳児・2歳児の乳児クラス向けに、ゲーム性がある室内遊びのアイデアを紹介しました。
雨の日が続く梅雨や、暑くて戸外に出られないこともある夏などは、室内遊びで簡単なゲームを取り入れると楽しく過ごせるかもしれません。
また、保育中にゲーム遊びを行なうときは、年齢に合わせてねらいを明確にしておくことが大切です。
親子レクレーションなどにも取り入れられるので、今回紹介したゲームを参考に室内遊びに活用してみてくださいね。
保育士バンク!新卒では、実習に役立つ情報から就活に関する情報まで幅広く公開しています。
「これから就活を始めるけれど不安がある」「1人で就活を進められる自信がない…」という方は、ぜひ保育士バンク!新卒にご相談ください。
完全無料でお使いいただけるので、ぜひこの機会に登録してみてはいかがでしょうか。
に登録してみてはいかがでしょうか。