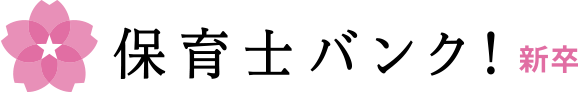保育学生さんや保育士試験を勉強中の方は、「ピアジェの発達段階」を学んでいるかもしれません。この理論は子どもの認知発達を年齢別の4段階に分けて捉えたもので、それぞれの段階における認知構造を知るのに役立つでしょう。今回は、前操作期や具体的操作期などのピアジェの発達段階を一覧表でわかりやすく解説します!テストに役立つ覚え方のポイントもまとめました。
 milatas / stock.adobe.com
milatas / stock.adobe.com
「ピアジェの発達段階」について知ろう!
ピアジェの発達段階は、児童心理学者のジャン・ピアジェ氏によって提唱されたものです。
ジャン・ピアジェ氏は1896年スイスに生まれ、10歳の時に発表した白スズメに関する論文が博物館の館長の目にとまり、彼のもとで放課後非常勤の助手を務めることになりました。
19歳でヌーシャテル大学動物学科を卒業し、ローザンヌ大学やチューリッヒ大学、パリ大学などで心理学を学んだ後、いくつかの大学で教鞭をとっていました。パリ大学では児童心理学講座の教授を務め、亡くなる1980年まで精力的に研究を続けていたようです。
50冊以上の本と500本以上の論文を発表し、心理学のみならず教育学・哲学・生物学の分野にも影響を与えたと言われています。
ジャン・ピアジェ氏の考え方はフロイトの「リビドー発達段階理論」、エリクソンの「心理社会的発達理論」と並んで3大発達段階説とされています。
押さえておきたいピアジェの4つの発達段階の特徴
 M-image / stock.adobe.com
M-image / stock.adobe.com
では具体的に、ピアジェの発達段階説にはどのような特徴があるのでしょうか。
認知の枠組みを「シェマ」と名付けた
ピアジェは、人が外界のものを認知する枠組みを「シェマ」と名づけ、それを学ぶ過程を「同化」「調節」「均衡化」の3つのステップに分けて考えました。
1.シェマの獲得
たとえば、子どもに5体の犬のフィギュアを見せ、それを「犬」と教えるとします。それぞれ個体は異なるものの、子どもは「犬」と言われるものの共通点を見つけるでしょう。これが「シェマ」の形成です。
2.同化
その後、大人が猫のフィギュアを見せたときに、子どもは以前の経験からそれを「犬」だと言うとします。
このように持っているシェマを他のものに当てはめようとする行為が「同化」です。
3.調節
しかし、子どもは大人から「これは猫だよ」と教わります。
すると子どもは新しい「猫」というものを認識し、犬のシェマと区別するようになるかもしれません。そうして既に獲得したシェマに変化を加えることが「調節」です。
4.均衡化
同化と調節のバランスを取りながらシェマを獲得していく過程です。
均衡化を繰り返すことで、子どもはより正しいシェマを形成していくと言われます。
それぞれの発達段階の間には質的な違いがある
ピアジェの発達段階においては、それぞれの段階は質的にまったく異なるものであるとしています。
ある段階から次の段階へ移行すると、表面的にできることが増えるだけでなく、それまでとは異なる思考のもとで行なうようになるのだとピアジェは考えました。
「ハイハイをしていた赤ちゃんが歩行できるようになった」という発達の違いを例に挙げると、「歩行」は「ハイハイ」が進展したものではなく、ハイハイとはまったく異なる質的に変化した行為と言えるそうです。
そのため、それぞれの発達段階における特徴には質的な違いがあると念頭においておくと、ピアジェの理論を理解しやすいかもしれませんね。
暗記ではなく本質的な理解に重点がおかれる
ピアジェは本質的な理解をしない「暗記のみ」の教育に違和感を覚えていたと言われています。
たとえば、「数」の概念を理解する第一歩として「1から10まで数を数えられる」ことは大切ですが、それだけではなく以下のように「数」の本質的な理解をしなければならないとしています。
【例】
- 10は3と7に分けることができる。
- 10から3がなくなると7になる。
- 10は5と5にも分けられるし、2と8にも分けられる。
- 10が10個あると100になる。
- つまり100を10個に分けると10の塊が10個できる。
こういった本質的な理解をすることが重要であるとピアジェは説いています。
理解が進むにつれて「10はほかにどんな数に分けられるだろう?」「7という数字は何で半分に分けられないのだろう?」といった疑問に子ども自身が気づくことがあるかもしれません。
そういった「能動的な思考」へつながっていくこともピアジェの考え方の一つです。
ピアジェが提唱する4つの発達段階
ピアジェは、認知発達段階を以下の表のように、年齢ごとの4段階に分けられると考えました。
| 発達段階 | 特徴 |
|---|---|
| 0歳~2歳:感覚運動期 | 五感の刺激を求めシェマの同化・調節を繰り返す。 |
| 2歳~7歳:前操作期 | 物事を自分のイメージを使って区別・認識できるようになる。 |
| 7歳~11歳:具体的操作期 | 論理的思考が発達し、他者の立場に立って行動できるようになる。 |
| 11歳~:形式的操作期 | 知識・経験を応用し、結果を予測して行動や発言ができるようになる。 |
このように、個人差はあるものの成長順序は普遍的であると唱えています。
上記の表をもとに、それぞれの発達段階についてくわしく紹介します。
感覚運動期:0歳~2歳
0歳~2歳の乳幼児期を、ピアジェは「感覚運動期」としました。
生後1カ月くらいまでは反射的な行動(モロー反射や吸てつ反応など)を使って外界と接触することで、シェマの土台を形成し始めるとしています。このとき、自分と他者の区別はありません。
成長とともに自らの身体を動かし、五感の刺激を求めて先述したシェマの「同化」と「調節」を繰り返していくようです。
周囲の人の声かけや世話、スキンシップなどで「他者と自分を区別すること」や「ものの形と役割を知ること」、「物事を予測すること」を覚えていくとしています。
この時期には、以下の認知機能が発達するようです。
循環反応
循環反応とは、「足や指をしゃぶる」「気になるおもちゃを何度も触る」など、同じことを繰り返し行うことで自分の身体やものの存在を確かめる反応です。
対象の永続性
たとえば、生まれてまもない子どもの目の前におもちゃがあったとして、大人がそれに布をかぶせて見えなくしてしまうと、子どもはおもちゃがなくなったと思います。
しかし、感覚運動期の後半には、布をかぶせられて視界から消えても、子どもはおもちゃがまだそこにあると認識できるようになります。
このように、人やものが目の前から見えなくなっても、状況に応じて「存在を予測」できるようになるのが対象の永続性を理解しているということになるでしょう。
シンボル機能(表象機能)
シンボル機能は、知っている物事を心の中に思い浮かべる機能です。
たとえば、犬のぬいぐるみや写真に写った犬などを見たときに、本物の犬を心に思い浮かべて「どちらも犬だ」と理解している状態を言います。
延滞模倣
延滞模倣とは、今ここにないものの様子を思い出して模倣する行動を指します。
ごっこ遊びがその一例と言えるでしょう。
これには、「表象機能」の発達が関係しているとされます。
物事を心の中に思い浮かべる表象機能が発達することで、物事を心の中でシンボル化して表現できるようになるようです。
前操作期:2歳~7歳
言語機能・運動機能ともに発達が著しい2歳~7歳頃を「前操作期」と言います。物事を自分のイメージを使って区別して認識できるようになるのが特徴です。
この時期には、創造力や想像力を働かせた「見立て遊び」や「ごっこ遊び」を盛んに行なうでしょう。
そして、以下の特徴が見られる傾向にあるようです。
自己中心性・中心化
この年齢における自己中心性とは、単なる「わがまま」とは異なります。
物事を相手の視点で捉えることが難しく、自分が見えているのと同じものが相手にも見えていると認識しているようです。
有名な例に「3つの山課題」という実験があります。
 図のような3つの山をAの視点から見た子どもは、Bの視点から見ている相手も「3つの山が見えている」と誤認してしまうという課題です。
図のような3つの山をAの視点から見た子どもは、Bの視点から見ている相手も「3つの山が見えている」と誤認してしまうという課題です。
このように、自分が把握しているものを中心に思考してしまう特徴を、ピアジェは自己中心性と名づけています。
保存性の未発達
論理的思考が未発達のため「物質の形状が変化しても、量や性質は変わらない」ということの理解も難しいかもしれません。
たとえば、大きなケーキを複数個に切り分けると、単純に個数が増えたことから食べられる量も多くなったと錯覚することなどが挙げられます。
そういった思考を保存性の未発達と言います。
アニミズム的思考
アニミズム的思考とは、まるで物事に命や意思があるように擬人化させて捉える傾向のことです。
たとえば、ぬいぐるみや食器、食べ物などに話しかけたり、それを使って一人芝居をしたりする様子が見られることを指します。
象徴機能
象徴機能とは、目の前にないものを別の何かで表現することです。
たとえば、目の前には実際にない車をブロックで代用して見立てる遊びなどが挙げられます。
象徴機能の発達により、見立て遊びやつもり遊びが盛んになっていくでしょう。
具体的操作期:7歳~11歳
論理的思考力が発達し、相手の気持ちを考えられるようになる7歳~11歳頃を「具体的操作期」としています。
数的概念が理解できるようになり、重さ・長さなどの比較も可能になるかもしれません。
この時期に見られる特徴は以下の2つとされています。
保存性の習得
具体的操作期になると、見た目に惑わされることはなくなります。
たとえば「大きなケーキを切り分けても、量は変わらない」「1リットルの水はどんな形や数の容器に入れても1リットルのまま」などと認識できるようになるのが保存性の習得です。
脱自己中心性
脱自己中心性とは、相手と自分とでは物の見え方が異なることに気づき、自己中心的な考え方から脱却し始めることを言います。
具体的操作期に入ることで、物事をさまざまな視点で見ることができるようになり、他者の視点の存在に気づくようになるでしょう。
形式的操作期:11歳~
11歳以降には、物事に筋道を立て、予測しながら考える論理的思考のほかに、抽象的思考ができるようになるかもしれません。この時期を形式的操作期と言います。
抽象的思考とは、具体的な事象や時間の流れに捉われずに「物事を広い視点で考える」ことです。自分で実際に体験したものではなくても、説明・映像などからイメージをえがき、頭の中で考えることができるでしょう。
また、これまでの知識や経験を応用して仮説を立て、結果を予測する仮説思考や推論といった思考力も発達するのが特徴と言えます。
「ピアジェの発達段階」を学ぶときのポイント
 ucchie79 / stock.adobe.com
ucchie79 / stock.adobe.com
保育士試験や養成校のレポートなどで扱われるピアジェの発達段階。
最後に、学習するときのポイントをまとめました。
認知発達段階全体を網羅する
保育士試験で出される問題は、ピアジェの唱える認知発達段階を理解しているか問われる傾向にあるようです。
全てを丸暗記するより、どの年齢でどのような認知発達の特徴が見られるのか、ニュアンスで覚えるほうが効果的かもしれません。自分の知っている子どもに当てはめてイメージしながら、理解を深めていくとよさそうです。
それぞれの段階の特徴を覚える
先述した4段階の特徴と詳細は、簡単に説明できるくらいまで覚えることがポイントになります。
実際の保育士試験では、「前操作期に起こる自己中心性とは何か」や、「具体的操作期に起こる保存性の習得とはどういったことか」といった問題が出題されることもあるようです。
それぞれの年代の子どもの、認知発達段階の特徴はどういったものかを中心に覚えておくと、試験で出されたときはもちろんレポートなどのテーマで用いるときもスムーズかもしれません。
ピアジェの発達段階を理解して、保育士試験や入職後に活かそう
今回は、ピアジェの発達段階について、前操作期や具体的操作期などの4段階に分けた詳しい説明や保育士試験に向けた学習ポイントなどを紹介しました。
ピアジェの発達段階理論は後の研究によって課題の実施方法に関する問題が指摘されています。固執しすぎないよう注意しつつ、子どもの発達や心理を捉える足がかりにしてみてくださいね。
保育士バンク!新卒では、保育実習や学生生活に役立つ情報から、新卒保育士の就活ノウハウも公開中。
- 不安だから早めに就活を始めたい!
- 学生OKな保育バイトってある?
などのお悩みはキャリアアドバイザーが相談に乗ります。
求人の紹介から履歴書の添削・面接対策まであなたの就活をフルサポート!
あなたらしく働ける園を保育士バンク!新卒で探してみませんか?