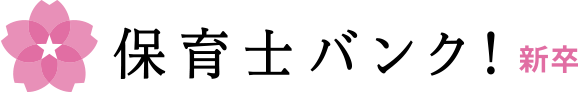保育士の目標設定の具体的な例文を知りたい方もいるでしょう。毎年立てる目標だからこそ「どう書けばいいのかな」「成長につながる内容にしたいけれど…」と悩むこともありますよね。今回は、日々の保育で実践しやすい経験別の目標設定のポイントや例文を紹介します。ダウンロードできる目標管理シート例付きです!あなたらしい目標を見つけ、保育士としての成長に役立てましょう。
 buritora / stock.adobe.com
buritora / stock.adobe.com
【例文あり】保育士の目標設定、どう立てる?成長につながる設定のポイント
保育園では毎年、1年間の目標を立てる機会があるでしょう。
いざ目標を立てようと思っても、「どんなふうに書けばいいのかな」「どんなことを意識したらいいのかな」と、迷ってしまう方もいるかもしれません。
そんなときは、日々の保育に取り組む姿勢や心がけを振り返りながら考えてみましょう。
特に、新人保育士さんの場合は、あまり目標を立てた経験がないので不安を抱くことがありそうです。
たとえば…
こうした目標は、日々の業務の中で意識しやすく、少しずつ保育士としての自信を積み重ねていくとよいですね。
目標を立てることは、これまでの自分を振り返り、今後の保育をよりよくしていくための大切なステップです。
まずは目標を立てる際のポイントをチェックしてみましょう!
<その1.保育に向き合う「姿勢」を大切にする>
目標を立てるときには、「どんな保育士でありたいか」「どのような気持ちで子どもと向き合いたいか」といった“姿勢”に目を向けてみましょう。
保育の現場では、子どもたちとの関わりはもちろん、職員同士や保護者とのやりとりも含めて、さまざまな人との関係性の中で仕事が進んでいきます。
その際に、どんな姿勢で保育に取り組むかは、自分自身の成長にも大きく関わるでしょう。
「子どもの思いに寄り添って声かけをしていきたい」「チームの一員として周囲と協力していきたい」など、自分の保育観や人との関わり方に対する意識を目標にするとよいですね。
<その2.日々の保育で意識できる目標を立てる>
目標は、立てて終わりではなく「日々の保育の中で意識し、実践できるかどうか」がとても大切です。
せっかく立てた目標でも、抽象的すぎたり実践の場面がイメージできなかったりすると、日常に活かすのが難しくなってしまいます。
だからこそ、「具体的にどう行動するか」をイメージしながら目標を立てることがポイントです。
たとえば、「子どもともっと関わる」という目標を立てる場合、「一日ひとりひとりに声をかける時間を意識してつくる」「子どものつぶやきに耳を傾けるようにする」といったように、日常的にできることを書き出してみましょう。
無理なく続けられる目標は、日々の保育を積み重ねるうえでの「達成感」や「自信」にもつながるでしょう。
<その3.園やクラスの状況に合わせて柔軟に考える>
保育の現場は、園の方針や子どもたちの人数、行事の多さなどによって状況が変わるでしょう。
だからこそ、目標を無理なく取り組める内容にすることが大切です。
たとえば、大きな行事が多い園では、「日々の記録をこまめに行い、行事の準備にゆとりを持たせる」といった工夫も必要でしょう。
また、子どもとの関係づくりに力を入れたい時期なら、「子ども一人ひとりに安心感を与えられる関わり方を心がける」といった目標も考えられます。
背伸びしすぎず、自分にとって重点的に成し遂げたい目標を掲げてみましょう。
保育目標の立て方のポイントを紹介しましたが、実際になかなか言葉が思い浮かばないこともありますよね。
ここからは経験別に保育士の目標例文を仕事との向き合い方や子ども・保護者への対応、職員同士の関係づくりなどに分けて、紹介します。
【保育士目標例文】新人1年目

新人保育士さんにとって、1年目は「仕事に慣れる」「園の雰囲気や流れをつかむ」といった段階でしょう。
最初から大きな目標を掲げるのではなく、日々の積み重ねを大切にできる内容にすることを意識するとよいですね。
【仕事の基礎を身につける】
はじめは「できることを少しずつ増やす」ことが大切です。日々の流れをつかみながら、仕事のルールや基本的な業務を丁寧に覚えられるような目標を立てましょう。
- 日常的にわからないことは積極的に質問し、先輩に確認するようにする
- 保育日誌や連絡帳の書き方に慣れ、不安な内容は先輩に相談する
- 園の一日の流れやルールを早く覚え、スムーズに動けるようになる
【子どもとの関係づくりを意識する】
子どもとの信頼関係を丁寧に築くために、関わる姿勢や声かけの仕方など、日常のふれ合いを大切にする視点で目標を考えてみましょう。
- 子どもの様子をよく観察し、気になる変化を先輩と共有できるようにする
- 子どもの思いや言葉を否定せず、まずはしっかりと受け止めることを意識する
- 毎日一人ひとりと目を合わせてあいさつや声かけを行うようにする
【保護者対応の基本を身につける】
保護者との関係づくりも、保育士にとって大切な仕事のひとつです。まずはあいさつや基本的なやりとりを丁寧に行えるよう、日常の中で取り組めることに目を向けるとよさそうです。
- 朝・夕のあいさつを丁寧に行い、笑顔で対応するように意識する
- 保護者の話に耳を傾け、不安や相談には先輩と連携して対応する
- 連絡帳や口頭での伝達において、子どもの様子をわかりやすく伝えられるように工夫をする
【職員同士のコミュニケーションを大切にする】
新人のうちは受け身になりがちですが、チームの一員として意識を持つことも大切です。積極的にコミュニケーションを取ることを意識すると、周囲との連携もしやすくなりそうです。
- 報告・連絡・相談を意識し、業務の引き継ぎや共有を丁寧に行う
- 自分から元気にあいさつや声かけをして、職員同士のコミュニケーションを大切にする
- 行事準備や掃除など、できることを見つけて積極的に取り組む
【保育士目標例文】2年目
2年目は、1年目で学んだ基礎を土台に、少しずつ自信を持って行動の幅を広げていく時期でしょう。
1年目を振り返りながら、次のステップに向けた目標を立ててみましょう。
【保育の実践力を高める】
2年目は1年目の学びをもとに、「自分で考えて動く力」を育てていきましょう。保育のねらいや子どもの姿を意識しながら、行動できるような目標を立てられるとよいですね。
- 活動のねらいを理解したうえで、保育中の声かけや関わり方を工夫する
- 子ども一人ひとりの発達や性格に合わせた関わりを意識する
- 子どもの様子に合わせて、次の保育内容の変更・提案をしてみる
【子ども理解を深める】
関わり方の幅を広げながら、子どもの気持ちにより深く寄り添えるようになるとよいですね。観察力や柔軟な対応力を養うことを目標にしてみましょう。
- 子どもの小さな変化に気づけるよう、日々の様子を丁寧に観察する
- 気になる子どもへの関わり方を先輩に相談し、自分なりの対応を試してみる
- 子ども同士の関わりにも注目し、仲立ちやフォローができるよう意識する
【保護者対応のステップアップ】
あいさつや基本的なやりとりに慣れてきたら、もう一歩踏み込んだ関わりを意識してみましょう。保護者との信頼関係づくりに向けた行動を目標にするとよいですね。
- 保護者と子どもの話を共有しながら、関係づくりを意識して会話する
- 連絡帳ではできる限り、コメントを残し、コミュニケーションを大切にする
- 保護者の不安や疑問を受け止め、必要に応じて先輩と連携して対応する
【職員同士の連携・役割意識を持つ】
2年目になると、まわりの職員の動きや保育全体の流れが少しずつわかってくるかもしれません。
自分の役割や立ち位置を意識しながら、チームの一員として行動していくことが求められそうです。連携を意識した行動や、職場の雰囲気づくりに関わる姿勢を目標にしてみましょう。
- 自分の役割を理解し、声をかけながら連携して動けるようにする
- 会話やあいさつを大切にし、気持ちよく働ける雰囲気づくりを意識する
- 1年目の職員に対して、自分が教わったことを伝えるように心がける
【保育士目標例文】3年目

3年目は、これまでに積み重ねてきた経験を活かしながら、保育の質を深めたり、後輩をサポートしたりする意識が求められる時期でしょう。
自分の保育にさらに磨きをかけつつ、チームの中での役割も広げていけるとよいですね。
【保育の質を高める】
子どもの姿に寄り添い、一人ひとりの個性や特性をふまえて、関わることができるようになるとよいですね。
ねらいや背景を意識した対応を増やし、保育に対する視点をさらに深められるような目標を立てましょう。
- 子どもの発達や興味関心に応じた活動を自ら考え、提案するようにする
- 活動の意図をしっかり持ち、子どもの様子に合わせて柔軟に対応する
- 子どもの行動や言葉の背景を考えながら関わるよう意識する
【後輩へのサポートや指導を意識する】
3年目になると、1・2年目の職員に頼られる場面も増えてくるでしょう。
自分が教わってきた経験を活かしながら、後輩が安心して働ける環境をつくれるとよいですね。
- 後輩の悩みや疑問に耳を傾け、自分の経験をもとにアドバイスする
- 保育中に後輩の様子を気にかけ、困っていることはないか確認しながらサポートする
- 他の職員が困っているときは自分から声をかけ、チームで支え合う雰囲気をつくる
【保護者との信頼関係を深める】
これまでに積み重ねた経験を活かし、保護者対応にも少しずつ余裕が出てくる時期かもしれません。より丁寧で安心感のある関わりを意識していきましょう。
- 保護者との日々のやりとりを通して、傾聴姿勢を大切にして信頼関係を築けるようにする
- 保護者の気持ちに寄り添い、不安や要望に対して誠実に対応する
- 子どもの姿や成長を具体的に伝えることで、家庭と園のつながりを意識する
【クラス運営やチーム全体を見渡す意識を持つ】
クラスやチーム全体の動きに目を向けることも3年目ならではの目標です。
自分の仕事だけでなく、周囲の様子を見て必要なフォローや声かけができると、より頼られる存在へと成長できるでしょう。
- クラス内の職員と連携を取りながら、保育が円滑に進むよう意識する
- 他クラスとの情報共有や相談にも積極的に関わるようにする
- 園全体の行事や方針に対して、自分から意見やアイデアを出してみる
【保育士目標例文】5年~7年目
5年~7年目は、保育士としての基本的なスキルや園での役割も安定してきた頃でしょう。
後輩への支援やクラス運営、職員間の調整など、保育の質とチーム全体への意識の両立が求められる時期です。
ここでは、より深い視点で保育と向き合うための具体的な目標例を紹介します。
【保育の質を高め、保育観を深める】
これまでの経験をふまえ、研修などで学んだことを活かしながら、子ども一人ひとりの育ちを大切にしましょう。
- 活動の計画にあたっては、子どもの発達段階や個々の興味をふまえた意図を持ち、保育内容に反映させる
- 日々の記録や振り返りを通じて、保育のねらいが実際の子どもの姿にどのように表れているかを見直す
- 乳児・幼児期に必要な活動を整理し、年間を通した保育構成の中でバランスよく取り入れる
【後輩育成や園内での関わりを広げる】
5年~7年目には、後輩にとって安心できる存在となり、日常的に声をかけ合いながら学びを支える姿勢が求められるでしょう。役割を意識し、園全体の雰囲気づくりに取り組んでいきましょう。
- 日々の業務の中で、後輩が不安そうな場面ではこまめに声をかけ、振り返りのきっかけをつくる
- 新人・若手職員が相談しやすい雰囲気をつくるために、日常的なあいさつややりとりを丁寧に行う
- 自分がリーダーや主任から教わったことを、自分なりの言葉で後輩に伝えていく姿勢を大切にする
【保護者にとって頼れる存在になる】
5年~7年ほど在籍していると、保護者からも“安心して相談できる存在”として見られる場面も多いかもしれません。
家庭環境や保護者の気持ちにも配慮した丁寧な対応を心がけましょう。
- 日々のやりとりの中で、子どもの育ちや家庭での様子とのつながりに注目しながら会話を行う
- 保護者の表情や声のトーンに注意を向け、不安や戸惑いがある場合は担任や上司と連携して対応する
- 子どものエピソードを通して、成長の様子や園での取り組みが伝わるような言葉を選んで伝える
【職員同士の連携体制や全体の保育を見渡す意識を持つ】
職員同士の信頼関係を育みながら、クラス運営だけでなく、園全体の保育の質を高める視点も少しずつ求められそうです。
日々の小さな連携や声かけを積み重ねることで、チームとしてのコミュニケーションが取れるような目標を立てられるとよいですね。
- 自分のクラス以外の行事や取り組みにも関心を持ち、必要に応じて他クラスの職員と情報共有を行う
- ミーティングや日々のやりとりの中で、保育内容に関する提案や意見を前向きに伝える
- 園全体の方針や取り組みに沿って、自クラスの保育の方向性を整理し、他職員との共通認識をもつ
【保育士目標例文】10年目

10年目は、これまでの経験を活かして“現場を支える側”としての視点を持つことが大切になるかもしれません。
保育士としての実践力に加え、職員育成・チームづくり・園運営への貢献といった広い視野での目標を設定するとよさそうです。
【園全体の保育の質を高める】
日々の保育をクラス単位でとらえるだけでなく、園全体の流れや方針にも目を向けることも大切です。
保育の方向性が園全体の目標ときちんとつながっているかを意識して、目標を立てるとよいでしょう。
- 園の保育方針と日々の子どもの姿を照らし合わせ、定期的に全体で共有する機会を設ける
- 保育の振り返りを通じて、クラスごとの人員のバランスを確認し、必要に応じて調整を提案する
- 外部研修で学んだことを他職員と共有し、意見交換の機会を大切にする
【積極的に人材育成・後輩指導に関わる】
後輩や中堅職員が成長できるよう、場面に応じたアドバイスや声かけを行うことも多いかもしれません。
「相談しやすい存在」としての信頼を築くことを大切にして、目標を立てていきましょう。
- 年間を通じて後輩の育成状況を把握し、育成方針や指導内容について園長と連携しながら進める
- 実習生や新任職員には、自分が指導を受けた経験を活かして、わかりやすく丁寧な説明を心がける
- 職員から定期的に保育の悩みや不安を聞く機会を設け、安心して相談できる環境を整える
【保護者との信頼関係を大切に、支援につなげる関わりを意識する】
日々の丁寧なやりとりに加え、家庭の状況や保護者の思いにも寄り添いながら、信頼関係をさらに深めていけるような関わりを意識していきましょう。
また、若手職員が保護者対応に不安を感じている場面では、支援や助言ができるように心がけることも大切です。
- 保護者の悩みや相談に耳を傾け、必要に応じて子育て支援の視点から関係機関や園内の連携につなげる
- 難しい対応が必要な場面では、冷静に状況を整理し、主任や園長とも連携しながら保護者と向き合う
- 後輩職員の保護者対応に付き添い、トラブルなどで仲立ちが必要なときは適切に対応する
【積極的に園運営に参加する】
10年目の方の中には、園全体の運営に関わる業務を任されることもあるでしょう。
現場の職員が働きやすいように、自分自身の役割を考えて、目標を立てるとよさそうです。
- 行事や年間計画の改善点を振り返り、課題解決に向けて職員同士で取り組める雰囲気をつくる
- 業務の効率化やICT活用など、現場負担の軽減につながるアイデアを具体的に提案する
- 園内の課題に対し、保護者・職員双方の視点から見直す取り組みをリードする
【例文付き】目標設定後の自己評価に役立つ、目標管理シートを活用しよう
経験別に目標設定の例文を紹介しましたが、1年間の目標設定後は、達成度を振り返る機会をつくることも大切です。
その際、活用したいのが「目標管理シート」です。
立てた目標に対する進捗や気づきを記録していくためのシートなので、自分の成長や課題に気づきやすくなり、次の目標にもつながるでしょう。
【目標管理シート例】
| 期間 | 目標 | 取り組んだこと | 子どもの様子 | 振り返り | 今後に活かすこと |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月〜6月 | 登園時に笑顔で声かけを行い、安心できる関係をつくる | 名前を呼んであいさつし、目を見て会話を心がけた | 不安な様子が減り、笑顔で登園する子が増えた | 日々のやりとりが、子どもに安心感を与えると感じた | 活動中や帰りの場面でも、一人ひとりへの声かけを続けていきたい |
| 7月〜9月 | 子どもの小さな変化に気づき、報連相をこまめに行う | 気になる言動はすぐにメモし、担任や先輩に共有した | 職員間で早めに対応できるようになった | 情報を共有することで、安心して保育ができると実感した | 忙しいときでも短く伝える工夫を続けていきたい |
| 10月〜12月 | 子どものつぶやきに耳を傾け、関係を深める | 自由遊びや移動中に自然に話しかけるようにした | 子どもが自分の気持ちを話してくれることが増えた | 日常の会話から信頼関係が深まっていくことに気づいた | 丁寧に聞く姿勢を意識して、関係づくりを続けていきたい |
| 1月〜3月 | 活動中の役割を意識し、職員間の連携を強化する | 行事前などに声かけや確認を積極的に行った | 準備がスムーズになり、落ち着いて当日を迎えられた | 自分の動きがチームの動きに影響することを強く実感した | 連携を意識しながら、まわりに声をかけていきたい |
目標管理シートのダウンロードはこちら
あくまでも一例なので、自分自身が記入しやすいようにアレンジしてみてくださいね。
また、年度末には、1年間の保育をふり返る「自己評価」を行う機会があります。
日々の気づきや取り組みを目標管理シートに記録しておくことで、自分の変化や頑張りが具体的に見えてくるでしょう。
自己評価の際にも目標管理シートを活用しながら、保育士としての成長やキャリアアップにつなげてくださいね。
保育士の目標例文を参考に自分に合った目標を立てよう
保育士が自分自身で立てる目標は、毎日の保育に向き合う“指針”となるでしょう。
自分の目指す姿や大切にしたいことを言葉にすると、日々の行動にも自信が持てるかもしれません。
特に、新卒の保育士さんにとっては「何を目標にすればいいの?」と迷うこともありそうです。
子どもとの関わり方や職員とのやりとりなどを通して、自分なりの「保育士の理想像」を考え、目標を立ててみてくださいね。
なお、保育士バンク!新卒では、保育に役立つ情報や遊びネタを配信しています。
また、就活・転職のサポートも実施しているので「もっと自分のキャリアアップにつながる園で働きたい」などの希望がありましたら、ご相談ください。
あなたが保育士として成長できる、楽しく働ける職場を一緒に見つけていきましょう。