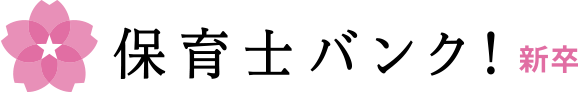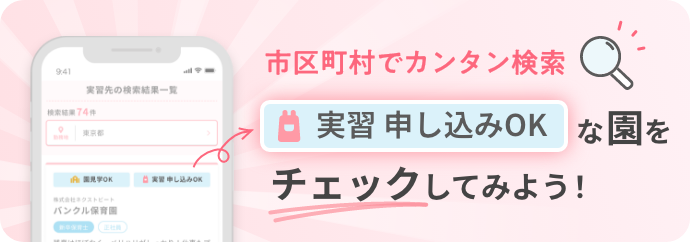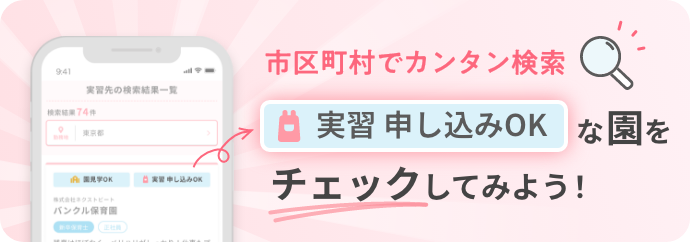保育実習での指導案は、部分実習や責任実習においてねらいを定めたうえで、環境構成や援助について立案します。子どもの姿をもとに絵本や製作など適切な活動内容を決めたり、興味を引き出す導入を考えたりするうえでも大切と言えるでしょう。今回は保育実習で役立つ、部分実習や責任実習の指導案の書き方を見本例とともに解説します。

takayuki/shutterstock.com
■目次
保育実習に必要な指導案とは
保育実習の部分実習や責任実習では、指導案を書くようです。
そもそも指導案とは、どのような書類なのでしょうか。
指導案とは
保育での指導案とは、子どもたちが意欲をもって活動に取り組むための働きかけや配慮を具体的にした計画書です。
まずは活動のねらいを定め、それに沿って主となる活動内容を決めます。
そのうえで、ねらいを実現するための環境構成や、子どもの活動の展開を望ましい方向に導いていくための保育士の援助などを肉付けし、分かりやすく具体的にしたものです。
指導案の種類
実際に保育士となり、保育園や幼稚園などで作成する指導案には、次のような種類があります。初めに年間計画に着手し、月案→週案→日案と、順を追って細かく作りこんでいく流れになります。
長期指導案
4月からの1年間を通して立てる「年間計画」と、年間計画をさらに月単位に落とし込んだ「月案」の2種類があります。
- 年間計画:4月~翌年3月までの1年間の生活を見通して立てる長期の指導案です。1年後の子どもたちの成長の着地点を明確にイメージして計画します。
- 月案:年間計画を具体化するために、1カ月の生活を見通して立てる指導案です。1年後の子どもたちの姿から逆算し、どのような過程を経ることで1年後の姿が実現できるかを落とし込みます。
短期指導案
月案を実施するために、週単位に落とし込んだ「週案」、さらに週案を1日単位に落とし込んだ「日案」があります。
- 週案:月案実施のために、継続性を考えながら1週間を見通して活動を具体化して立てる指導案です。
- 日案:その日の保育をどのように展開するのか、1日の子どもの生活時間を見通して細かく立てる指導案です。責任実習で提出する指導案がこの日案になります。
- 部分案:1日の保育のなかで主活動のみ、帰りの会のみなど、部分的な活動計画を立てる指導案です。部分実習で提出するのは、この部分指導案になります。
保育実習での指導案作成の手順
子どもたち一人ひとりが、安全な活動を楽しめるようにするには、しっかりと指導案を立てておく必要があります。
しかしどんなにきちんとした計画を立てても、ハプニングはつきものです。臨機応変に対応できるような事前予測や、安全を確保するための細心の注意を払うようにしましょう。
手順1.子どもの様子や園の決まりの確認
指導案を立案する前に、実習園の決まりや配属クラスの様子、受け持つ子どもたちの様子などを、事前に確認しておきましょう。
<確認するポイント例>
- 子どもの名前の呼び方(姓か名前か)
- 子どもの友だち関係
- クラスの雰囲気
- 実習施設で現在取り組んでいることや遊び、はやっていること
- クラスで注意が必要な子どもの情報
- 施設の決まりやルール
- 配属クラスの中のきまりやルール
- 教材や教具の置き場所や使い方
- 昼食準備やトイレの行き方
手順2.指導案の立案
指導案は保育実習先の園や施設の指導案の形式に沿って立案しましょう。特に指示がなければ、所属している学校で学んだ形式で立案します。
保育実習中に観察した子どもの姿や好みなどから、ねらいを立てて、安全に楽しめそうな活動を考えましょう。
このとき、年齢に合ったねらいや内容を立てるためにも、保育所保育指針などを見ながら5領域を意識した指導案を考えることが大切です。
手順3.指導案の修正
保育園では、もともと長期計画に沿った流れで週案・日案が立てられています。
その流れから逸れないようにするために、保育実習の指導案は実施日の1週間ほど前に担当の先生に提出し、アドバイスを受けるとよいでしょう。
1度目の提出後、指導された内容をもとに再考し、実施日の3日ほど前に再度提出する流れが多いようです。
手順4.副案の作成
天候は子どもの生活や遊びの内容に大きく影響します。
外遊びなど天候で左右されるような保育内容やスケジュールには、悪天の場合の代替えとなる「副案」を用意しておく必要があるので注意しておきましょう。
手順5.指導案に沿った教材、教具の準備
指導案を立案し担当保育者からのチェックが済んだら、実習中に使用するための教材や教具の準備をし、それらの安全性を確認します。
用意に時間がかかるもの
製作を行う場合、牛乳パックや空き箱など準備に時間がかかるものは、1週間前には子どもの家庭に連絡し回収する必要があります。
前もって担当の先生にお願いしておくとともに、通常よりも前倒しの指導案の提出が必要になるでしょう。
教材の数
教材の数は子どもの人数分、保育士と実習生の人数分、失敗分などを含めて、多めの準備が必要です。
保育実習(部分実習・責任実習)の指導案の書き方

leungchopan/shutterstock.com
保育実習で作成する指導案のフォーマットに、学校や園によってさまざまな形式がありますが、おおむね次のような項目になります。
<指導案のフォーマット見本例>

指導案に必要な「ねらい」
「ねらい」は、保育実習での実習期間を通して、子どもたちに身につけてもらいたい姿を具体的にしたもので、その際に知ってほしい心情・意欲・行動なども含まれます。
【ねらいの書き方のポイント】
- 子どもの発達に即して何を育てるのか
- 子どもの生活に即した体験が得られるか
- 自分は子どもの何が知りたいか など
活動内容
「活動内容」は、ねらいを達成するために指導していく事柄で、具体的な活動はもちろん、活動を通して体験される、達成感や成就感、満足感や充実感、などといった内面的なことも含まれています。
【活動内容の書き方のポイント】
- 子どもが興味をもって取り組むか
- 内容の調和がとれて発展的か
- 内容に偏りがなく関連性があるか
- 時季、社会生活行事を取り入れているか
環境構成と準備
保育環境の構成とは、「ねらい」や「内容」を明確に設定し、必要な援助や環境をさらに具体的にしていくことです。
ねらいに沿ったいくつかの環境を組み合わせ、子どもが自らかかわりたくなるような環境を作っていきましょう。
また、環境構成を考える前に、施設の環境、用具、材料の安全性などをチェックする必要があります。
【子どもが成長するうえで必要な環境例】
- 安全で安心できる環境
- 発達に応じた環境
- 興味や欲求に応じた環境
保育形態・編成形態・対象児童の年齢
指導案は子どもの年齢や数、男女比、季節、時期、天候によって、書き方が異なります。
また、今後の保育活動でPDCAサイクルを回すために重要な資料でもあります。
どのような状況のもと、どのようなねらいで立てたのか、その結果はどうだったのかを振り返り、漏らさず記入しましょう。
【記録欄の書き方】
- クラスの子どもの人数
- 個人かグループか
- 形態は一斉(設定)保育か、自由保育で進めるか
保育の流れと時間配分
子どもの1日の流れを把握したうえで、生活に即した取り組みを計画します。
1つの活動に子どもたちがどのくらい意欲をもって活動できるか、観察実習などの経験をもとに時間の目安を決めましょう。
また、活動の流れは、子どもの気持ちにメリハリやリズムをつけることも大切なので、そういったことにも配慮しながら立案してくとよいですね。
子どもたち一人ひとりが十分に自分を発揮でき、実習生自身の個性も十分に出せるような柔軟性のある指導案を立案しましょう。
導入・展開・まとめの進め方
子どもが活動に興味をもつための導入や、活動の流れを作る展開の方法などを書きましょう。
【導入・展開・まとめの書き方例】
- 絵本やペープサートなど視覚教材を使って子どもの目を惹く導入を行う
- 活動で取り入れる題材について、子どもに質問してみる
- 子どもに考えるきっかけを与える問いかけをする
- 上手にできている子どもに見本になってもらう
- 一人ひとりが活動に満足し、よろこべるようなまとめをする
子どもの反応、発案をどのように受け止め、それをどう展開(発展)させたらいいのかを考えられるとよいですね。
予想される子どもの姿
予想される子どもの言葉や動きなどをあらかじめ考えておき、記入しましょう。
【予想される子どもの姿の書き方】
- 子どもが楽しく自発的に活動するには、どのような言葉がけをして意欲を満たしたらよいのか
- 子どもの意欲を高めるためにはどんな働きがけが必要なのか
- 子どもは活動のどんな部分に関心を示すか
- 活動のなかに、子どもにとって難しい部分、簡単過ぎる部分はないか
指導案で子どもの姿を予想するには、普段から子どもたちのことをよく観察しておくことが求められます。
保育実習という限られた期間ではありますが、一人ひとりの特徴や性格を把握し、具体的に考えることが大切です。
保育実習(部分実習・責任実習)の指導案の記入例
次に、お月見団子の製作活動を例とした指導案を紹介します。
保育実習の部分実習や責任実習で参考にしてみてくださいね。
部分実習の記入例

例にある製作の指導案では、道具の怒方や、教え方、導入の方法まで詳しく書く必要があります。
作成例を参考に、ねらいや子どもの姿、環境構成をしっかりと記入しておきましょう。
責任実習の記入例

責任実習では、活動の合間をどのように過ごすかや、そのときの環境構成も大切になります。
保育実習を通して、担任の保育士さんの動きを見ておきましょう。
また、指導案は立案すること以上に、実践後の振り返りと考察が重要です。
指導案の段階で想像できなかったことや、立案したもののできなかったことを一つひとつ振り返り、どうしてそうなったのかを考察して、次の指導案に活かしていきましょう。
保育実習(部分実習・責任実習)の指導案作成のポイント
保育実習には部分実習と責任実習があり、それぞれ指導案を作る際に注意するポイントがあります。
部分実習の指導案のポイント
部分実習とは
部分実習は1日の保育の流れのなかで、ある一部分だけを自分の指導のもとで保育を行う実習です。
自分で準備した活動が、どのように子どもたちに受け止められているか、子どもの反応や行動を正確に捉えられるように十分観察しましょう。
その結果を実習日誌に記録することで、責任実習の際の指導案に生かすことができます。
部分実習での活動内容
保育園や幼稚園で1日を通して行われる、朝の会、帰りの会、絵本の読み聞かせ、製作、遊びなど、さまざまな活動のなかから実習のために学びたい活動を選びます。
責任実習の前に経験しておきたい活動内容など、よく考えて活動を考えましょう。また、担当する子どもの年齢や季節に合わせた活動内容にすることも大切です。
部分実習での子どもの姿
部分実習の場合、1日の保育の流れをいったん中断することになるので、活動に入る前の子どもの動き、その後の子どもの動きをよく捉えることが大切です。
絵本や手遊びを使って、しっかり導入を行うことでスムーズに部分実習に移れるかもしれません。
部分実習での立案の注意点
指導案を立てるにあたっては、配属されたクラスの担当保育士さんに相談しましょう。
保育士さんが立てた月案や週案の流れに沿って立案するのか、課題を与えられて立案するのか、実習生が独自に、しかもその日のための日案でよいのかなど、細部にわたって確認することが必要です。
責任実習での指導案の書き方
責任実習とは
責任実習では、クラスの担任として1日のすべての保育を担当します。
責任実習での活動内容
部分実習で学んだ活動や遊びだけでなく、子どもの健康状態の確認や給食、着替え、排泄、午睡(昼寝)など、生活全般についての配慮が必要です。
責任実習での子どもの姿
責任実習では、主活動以外にも、片付けやトイレ、部屋の移動などのつなぎの時間に子どもがどんな動きをするかをしっかり考えておきましょう。
子どもの姿をしっかり予想して、それに対する援助方法も書き残しておくとよさそうです。
部分実習での立案の注意点
責任実習では活動と活動の間のつなぎの時間の子どもの動きが重要になります。
絵本の読み聞かせや手遊びなどを用意して、みんなが楽しく待てるような工夫をするとよいですね。
また、1日の指導計画作成から実際の保育までを一貫して行うため、念入りな準備が必要です。指導案の提出期限に間に合うよう、余裕をもって作成に臨みましょう。
保育実習の指導案は実習日誌の記録とセットで振り返りを
今回は、保育実習の責任実習や部分実習で提出する指導案の書き方について紹介しました。
部分実習では絵本の読み聞かせや製作など一部の活動を、責任実習では担任として1日の保育を任されます。
指導案ではしっかりとねらいを立てたり、子どもの姿を予想したりして、援助方法を考えていきましょう。
指導案の書き方や作例を参考に、保育実習に活かしてみてくださいね。