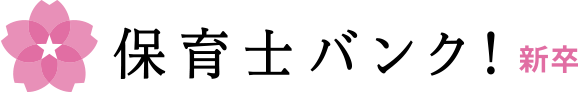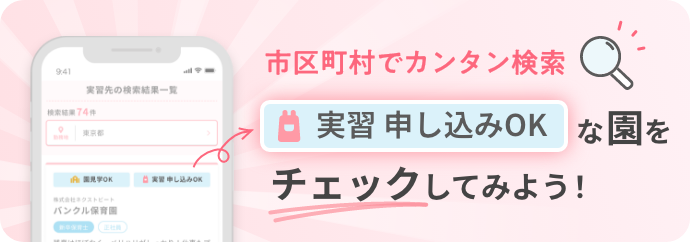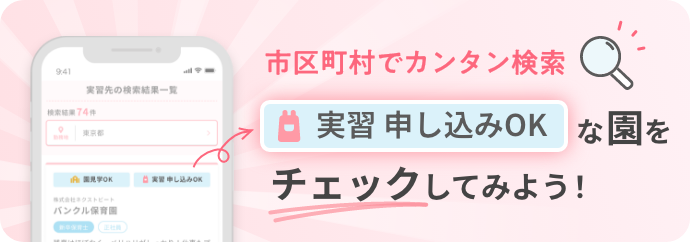保育実習や幼稚園実習の最終日に、クラスの子どもたちにお礼を兼ねてプレゼントを贈りたいと考える方も多いかもしれません。形に残る手作りの折り紙やメダル、思いをこめたメッセージカードなどを渡せたら素敵ですよね。今回は、簡単な手作りプレゼントの作り方やメッセージの文例をまとめました。また、用意する際の注意点についても紹介します。
 arhendrix / stock.adobe.com
arhendrix / stock.adobe.com
保育実習・幼稚園実習の最終日の子どもたちへのプレゼント
保育実習や幼稚園実習でお世話になった子どもへの愛情や感謝の気持ちを伝えられる手作りプレゼント。
最終日に、折り紙や手作りおもちゃ、メッセージカードなどを贈るのが主流ですが、どのようなプレゼントがよろこんでもらえるのでしょうか。
まずは、そもそもプレゼントを贈ってもよいのかなど基本的なことから見ていきましょう。
そもそも保育実習・幼稚園実習でプレゼントを渡してもOK?
実習生さんからのプレゼントは、一般的に承認してくれる保育園や幼稚園は多いようです。
園の方針によっては、子ども一人ひとりに渡すことを禁止している場合や、一部のクラスにだけ特別な物が配られるのをよしとしないケースもあるでしょう。
また、プレゼントを手作りするには多くの時間や労力が必要なため、「保育実習や幼稚園実習中はプレゼントの準備ではなく、学びに集中してほしい」と考える指導者の方もいるようです。
感謝の気持ちを表す方法はプレゼント以外にもあるため、その場合は実習園の方針に従うようにするとよいですね。
保育実習・幼稚園実習のプレゼントは絶対に必要?
なかには、プレゼントの有無が実習の評価につながるのではと考え、不安に感じる方もいるかもしれません。
実習の評価基準は実習態度や日誌の内容などがメインです。
プレゼントをあげた・あげないで評価が変わることはないようなので、安心してくださいね。
保育実習・幼稚園実習に適しているプレゼント例
実習のお礼として子どもたちに渡すプレゼントには、どんなものが適しているのでしょうか?
OK例:手作りできるもの
基本的には、安価で手に入る身近な材料を使った手作りの実習プレゼントが一般的なようです。
例えば、折り紙やフェルトなどを使った手作りメダルや腕時計など、身につけられるような手作りの制作物は子どもがよろこんでくれるでしょう。
また、色紙やカードなどに、一人ひとりの子どもへのメッセージを書いて渡すのも、思い出になるプレゼントの1つです。
NG例:購入した市販品
基本的に、お金をかけて購入した既製品を実習のプレゼントにするのは避けたほうがよいようです。
ほかにも、食べ物がプレゼントのNG例として挙げられます。
アレルギーのある子どもへの配慮や、衛生上の問題があるため、保育実習のプレゼントとしては贈らないようにしましょう。
保育実習・幼稚園実習でプレゼントを贈る前に確認すること
 yamasan / stock.adobe.com
yamasan / stock.adobe.com
保育実習や幼稚園実習のプレゼントを用意する際に確認しておくポイントをまとめました。
手作りプレゼントを贈る対象は?
子どもたち一人ひとり
配属されたクラスの子どもたち全員にプレゼントを用意するパターンです。メダルや手作りおもちゃなど、一人1つプレゼントが行き渡るように人数分製作します。
材料費や製作時間がかかるため、このケースでは計画的にプレゼント作りを進められるように早めに準備をしておくとよいでしょう。
担当したクラスに一つ
クラスの子ども全員が楽しめるよう、クラス宛てのメッセージカードや写真立て、壁面などを用意する場合もあるようです。
みんなで遊べる手作りおもちゃや、保育室の整頓に役立つおもちゃ箱などもよいでしょう。
数日に分けていくつかのクラスに入った場合には、製作時間を考慮して、各クラスに宛ててプレゼントを用意するのがよいかもしれません。
プレゼントはいつ渡す?
最終日のお別れ会など
プレゼントは実習の最終日など、締めくくりの場で渡すことが多いようです。
お別れ会や帰りの会などのタイミングで、プレゼント用に時間を設けてもらいましょう。
プレゼントを渡すことへの了承を事前に得たうえで、お別れ会のどのタイミングでプレゼントを渡すか考えておくとよいですね。
挨拶が終わったタイミングで
挨拶の前にプレゼントを渡すと、子どもの興味や集中がそちらに移ってしまうため、挨拶を終えてからプレゼントを手渡すようにするとよさそうです。
その際、実習中に子どもたちといっしょに過ごした感想や思い出、感謝の気持ちなど、子どもたちへの思いをしっかり伝えたうえで贈ると気持ちをより伝えられるでしょう。
プレゼントを手作りするときの配慮点
プレゼントを渡す前に、幼稚園や保育園側に確認を
プレゼントを手作りする前に、子どもたちに渡してもよいのかを、担当の先生や園長先生に確認する必要があります。
プレゼントの準備期間を踏まえて、実習の事前オリエンテーションで確認しておくのがスムーズでしょう。
実習中に聞く場合には、最終日の1週間ほど前に質問しておくとよいですね。
子どもの年齢に合わせたプレゼントを
保育実習や幼稚園実習のプレゼントでは、年齢によってよろこんでもらえる品物が異なるようです。
0歳児から2歳児の乳児クラスでは、安全性を配慮したフェルトなどのやわらかい素材が適していると言えます。
万が一子どもが舐めたり口に入れたりしても比較的危険が少ない素材で作る配慮をしましょう。
3歳児・4歳児・5歳児クラスでは、折り紙で作ったメダルや手裏剣などの手作りおもちゃが人気のようです。
文字に興味を持つ年齢になると、簡単な手書きのメッセージもよろこんでくれるかもしれませんね。
手作りする際には材料や金額が適切なものを
クラス全員分など、まとまった数のプレゼントを作る場合は、材料費がかかりすぎないように工夫しましょう。
お金のかかったプレゼントは、実習生さんの負担を気にして、保育園側に気を使わせてしまうおそれがあります。
折り紙、画用紙、紙コップや紙皿、フェルトなど、身近にあり安価で求めやすいもので手作りするとよいですね。
必ず人数分用意し、色や絵柄など差が生じないように
子ども全員にプレゼントを渡す場合、もらえない子が出てこないよう、必ず人数分を用意します。
色や柄に違いがあると、「そっちの色がいい」と取り合いになってしまう可能性もあるため、デザインは統一したほうがよいでしょう。
また、キャラクターデザインを保育に使用しない方針の保育園もあるようです。プレゼントでキャラクターの柄を使用したい場合は確認を取っておくとよいですね。
保育実習・幼稚園実習に贈る手作りプレゼントのアイデア
実習でプレゼントを渡すときのポイントがわかったところで、手作りできるプレゼントのアイデアを見ていきましょう。
手作りメダル、身につけて遊べるグッズ、手作りおもちゃとジャンル別にまとめました。
手作りメダルのプレゼント
まずは、手作りメダルのプレゼントの作り方を紹介します。
リボンや紐を通して首からかけられるようにすれば、0歳児から5歳児まで、どの年齢の子どももよろこんでくれるでしょう。
桜の折り紙メダル
両面に色がついている折り紙、もしくは2枚の折り紙を貼り合わせたものを使って、素敵なさくらのメダルを作ることができます。
春の実習にぴったりなプレゼントですね。 (詳しい説明はこちら)
紙コップの写真付きメダル
紙コップの底の形を利用して、写真つきのメダルを作ることができます。
真ん中には写真の代わりに子どもへのメッセージを書きこむこともできますよ。 (詳しい説明はこちら)
身につけて遊べる手作りプレゼント
時計やブレスレットなど、身につけられるアイテムは子どもたちに人気のようです。
記念に残るかわいらしいアイテムの作り方を見ていきましょう。
折り紙の腕時計
折り紙1枚で腕時計を作ることができます。
文字盤をつける立体的な部分や、ベルト部分も再現でき、しっかり手首に装着することもできますよ。(詳しい説明はこちら)
紙コップで作るアラーム腕時計
鈴の音が鳴る様子が楽しいアラーム腕時計です。
文字盤や長針・短針はもちろんのこと、ベルトをかけるところもきちんとある、本格的な腕時計です。
時計に興味を持ち始める4歳児や5歳児クラスにプレゼントしてみるとよいかもしれません。(詳しい説明はこちら)
モールで作るアクセサリー
秋の実習では、季節の素材のドングリとモールを使って、ブレスレットや指輪、メガネをプレゼントするのもよいでしょう。
ドングリの代わりに大きめのビーズを使ってもかわいく仕上がりそうですよ。
動画にあるように、3種類のアイテムを作ることができるため、子どもの好みに合わせてどれか1種類を作ってみてくださいね。(詳しい説明はこちら)
手作りおもちゃのプレゼント
実習が終わっても繰り返し遊べる手作りおもちゃのアイデアをまとめました。
折り紙の手作りコマ
3つのパーツでよく回る、折り紙のコマが作れます。折り紙で作ったとは思えないほど、本格的なのでしっかり回りますよ。
コマを回して楽しめる2歳児以上のクラスでプレゼントするとよいかもしれません。(詳しい説明はこちら)
色が混ざる混色コマ
交互に色をつけたコマを速く回転させると、それぞれの色が混ざったように見えます。
身近な素材を使って簡単に作ることができるので、費用面も抑えられそうですね。
上手に扱えるようになる4歳児や5歳児でのプレゼントに活用するとよいでしょう。(詳しい説明はこちら)
折り紙手裏剣
子どもたちに大人気の手裏剣を実習のプレゼントに活用するのもよいですね。忍者ごっこだけでなく、ひもやリボンを通せばメダルとして首にかけることもできます。
キラキラ光るホログラムやホイルの折り紙を使えば、プレゼントの特別感を演出できそうです。(詳しい説明はこちら)
プレゼントのなかでも手作りメダルにはさまざまな作り方があります。以下の記事を参考に、手作りメダルを実習でプレゼントしてみましょう。
保育実習・幼稚園実習でメッセージカードをプレゼントするときの例文
担当クラスの子どもが文字に興味を持っているようであれば、気持ちが伝わるメッセージカードも素敵なプレゼントになるでしょう。
メダルや手裏剣といった手作りプレゼントに、メッセージを添えて渡す工夫をもできますね。
メッセージカードを書くときのポイント
ひらがなで書き、簡潔な内容にする
メッセージは子どもたちが読みやすいよう、ひらがなを使って書くことがポイントです。
長いメッセージだと理解するのが難しい場合もあるので、一言か二言程度で簡潔にまとめるよう心がけましょう。
子どもの名前を添える
メッセージの冒頭には、「〇〇ちゃん」や「〇〇くん」と、子ども一人ひとりの名前を書いておくと、自分だけのメッセージとして特別感が演出できるようです。
手作りプレゼントを贈るときにも、1つひとつ名前を書いて渡すのもよいですね。
【年齢別】保育実習・幼稚園実習のお礼のメッセージ例文
子どもたちに向けた、保育実習や幼稚園実習のお礼メッセージの例文を紹介します。
プレゼントを贈るときの参考にしてみてくださいね。
0歳児、1歳児
「にっこりえがおがとってもすてきな〇〇くん。せんせいのてあそびをなんどもきいてくれたことが、ほんとうにうれしかったよ。いっしょにあそんでくれてありがとう。たくさんあそんで、げんきにおおきくなってね。」
2歳児、3歳児
「まいあさげんきにあいさつしてくれる〇〇ちゃん。おおきなこえに、いつもげんきをもらっていました。〇〇ちゃんのあかるいえがおが、せんせいはだいすきだよ。またあそびにくるね。」
4歳児、5歳児
「〇〇ちゃんとは、たくさんなわとびのれんしゅうをしたね。はじめて10かいせいこうしたときは、せんせいもとってもかんどうしたよ。これからもいろんなことにちょうせんして、ますますすてきなおねえさんになってね。」
言葉遣いや書き方に配慮しながら、子どもたちとの思い出に残るエピソードをもとに、メッセージを書いてみましょう。
保育実習・幼稚園実習のプレゼント選びは自分にも園にも負担のかからない配慮を
今回は、保育実習や幼稚園実習のプレゼントのアイデアや、贈るときのポイント、メッセージ例文を紹介しました。
「子どもたちに感謝を伝えたい」という気持ちを、手作りプレゼントに込めることは、実習生さんにとっても素敵な思い出になるかもしれません。
プレゼントの規定やあげるタイミングなどは園の方針によって異なるので、子どもたちに平等によろこんでもらえることを前提に手作りするとよいでしょう。
プレゼントのアイデアを参考に、実習での思い出や感謝の思いを伝えられるとよいですね。
「保育士バンク!新卒」では、実習で使える遊びネタや指導案の作成方法などを配信中!
また、保育学生さんの就活のサポートも実施しています。
あなたらしく働ける職場をいっしょに探すサポートをいたしますので、お気軽にご相談ください。