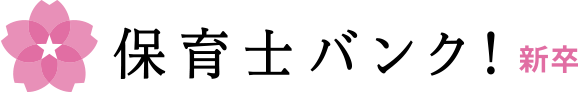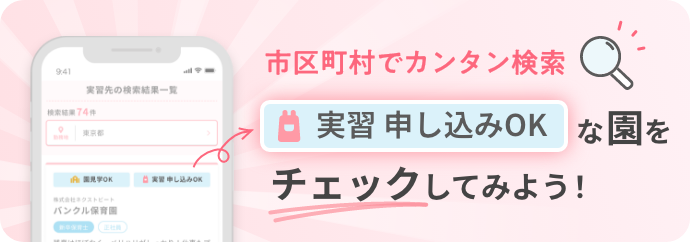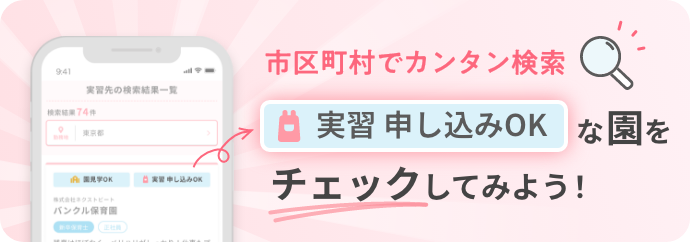保育実習や幼稚園実習の感謝を伝えるお礼状。例文や書き方のポイントを参考に、オリジナルで作成したいと考える保育学生さんもいるでしょう。今回は、保育実習や幼稚園実習のお礼状作成に役立つ例文を、送る相手別に紹介します。また、エピソードや時候の挨拶、締めの言葉などからなるお礼状の基本的な構成と、書くときのポイントを紹介します。
 hanack / stock.adobe.com
hanack / stock.adobe.com
保育実習や幼稚園実習のお礼状には何を書く?
保育実習や幼稚園実習後、感謝を伝えるためにお礼状を送りたいと考えている保育学生さんもいるでしょう。
しかし、どんなことを書けばよいのか、書き方のマナーなどがわからないと作成するのは難しいかもしれません。
お礼状でメインの内容となるのは実習先の園への感謝ですが、部分実習や責任実習などを終えて感じた自分の成長、今後への抱負などを添えて書くとよいでしょう。
保育実習を通して学んだことやエピソードとあわせてお礼を伝えれば、読み応えのあるお礼状になり、園の方も受け入れてよかったと感じてくれるかもしれません。
ただし、お礼状はかしこまった手紙のため、きちんとした構成を押さえたうえで書くことが大切です。
具体的な例文を紹介する前に、まずはお礼状の書き方から見ていきましょう。
【項目別】保育実習や幼稚園実習のお礼状の書き方
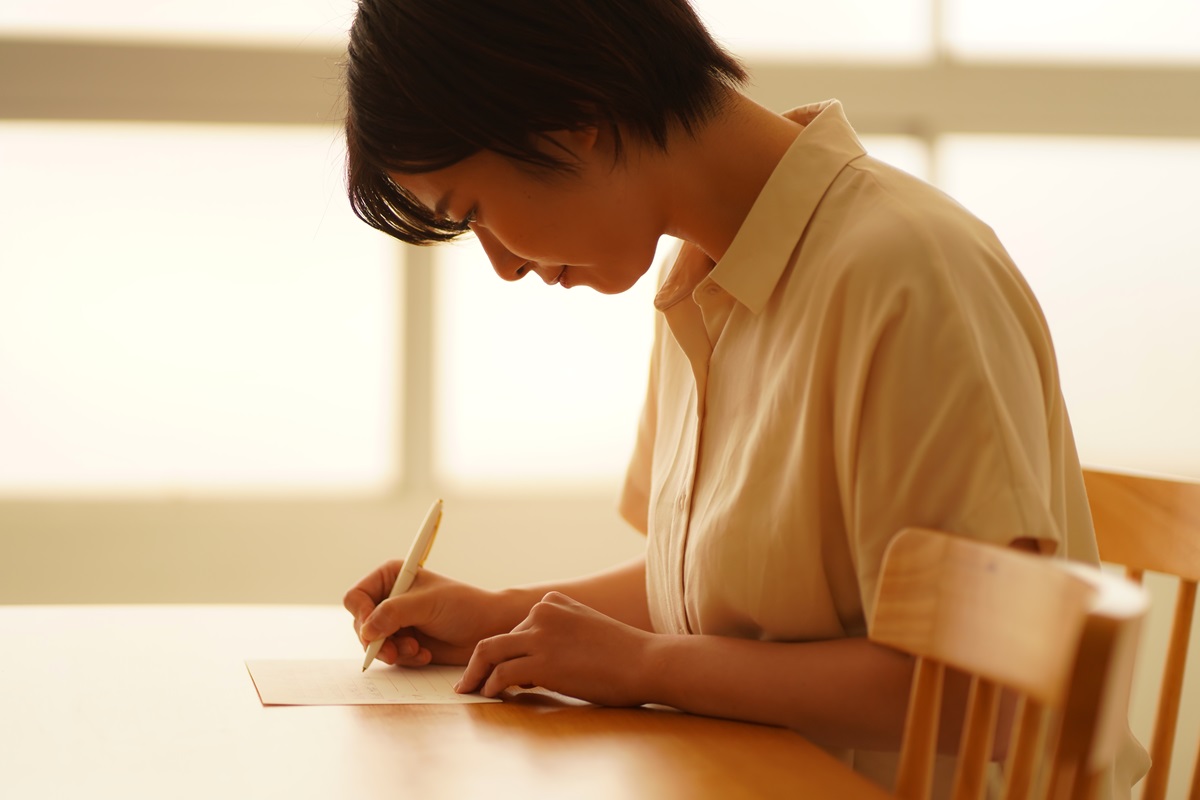 yamasan / stock.adobe.com
yamasan / stock.adobe.com
ここでは、お礼状の基本構成(前文、主文、末文、後付け)に沿って、項目ごとに書き方のポイントを紹介します。
前文
お礼状における前文は、頭語、時候の挨拶、安否の挨拶から成り立ちます。
頭語
頭語とは、手紙の一番初めにくる「こんにちは」といった挨拶にあたる言葉です。
一般的に「拝啓」や「謹啓」「謹白」などがあり、「謹啓」や「謹白」などがより改まったシーンで用いられるとされています。
頭語は、お礼状の末文に据える結語とセットで使うということを覚えておきましょう。
時候の挨拶
頭語の次にくるのが時候の挨拶です。
時候の挨拶とは、季節を表す言葉を用いた書き出しのことで、1月から12月までの季節ごとに書き分けます。
1月:年が明け、まだ来ぬ春が待ち遠しく感じられます
2月:立春とは名ばかりでまだまだ寒い日が続いております
3月:寒さの中に春の気配を感じる頃となりました
4月:桜の花のたよりが聞かれる頃になりました
5月:田を渡る風が気持ちの良い季節となりました
6月:あじさいの色が美しく映えるころとなりました
7月:降りしきる蝉の声に夏の盛りを感じる頃になりました
8月:秋まだ遠く、厳しい残暑が続いています
9月:朝の空気に爽秋の気配が感じられる頃となりました
10月:いよいよ秋も深まって参りました
11月:庭の紅葉も終わりを告げ、すぐ近くに冬の気配を感じる頃となりました
12月:年の瀬の、寒さの身にしみる季節となりました
時候の挨拶は季節や月によって異なるため、お礼状を送る時期にあわせて書きましょう。
3月であれば桃の花にふれたり、9月であれば残暑が残る気候について書いたりすると、季節感のある挨拶になりそうですね。
安否の挨拶
頭語の次に安否の挨拶がきます。
安否の挨拶とは、受け取り手の安否を尋ね、健康を気遣う言葉です。
- 皆様、お元気でお過ごしでしょうか。
- 園長先生や皆様にはお変わりなくお過ごしのことと存じます。
- 皆様には健やかにお過ごしのこととお喜び申し上げます。
- 皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
園長先生や園の先生方に送る場合は「皆様」または「貴園」と書くとよいでしょう。
園長先生や指導担当の先生一人に送る場合でも「皆様」を使うことができますが、「◯◯先生」「◯◯様」と記す場合もあるようです。
主文
主文では、実習の感謝と簡単なエピソードを記しましょう。
お礼
「この度は」「さて」といった起こし言葉を使って感謝の言葉へとスムーズにつなげます。
この度は、お忙しい中◯日間にわたり保育実習という貴重な学びの機会を与えていただきまして、ありがとうございました。
先日は、お忙しいところ貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。
まずは保育実習を受け入れてもらったことへのお礼を伝えましょう。
エピソード
実習を通して印象に残っていること、学んだことなどのエピソードを書いていきましょう。
保育実習後に感じた課題やこれからに活かしたいこと、どんな保育士になりたいかなど今後の抱負を具体的に書けば、オリジナリティのあるお礼状になり先生方にもよろこんでもらえるかもしれませんね。
末文
末文は締めの挨拶と結語から成り立ちます。
締めの挨拶
主文を書き終えたら締めの挨拶を書きましょう。
締めの挨拶とは手紙を締めくくるための言葉で、相手の健康などを気遣う言葉を添えるのが一般的です。
お礼状では、締めの挨拶として「末筆ながら」や「末筆ではございますが」から書き始め、園の発展や先生方の無事、健康を祈る言葉を添えましょう。
結語
結語は手紙の最後に来る「それではまた」といった挨拶を伝える言葉です。
先程紹介したように、頭語と対になる言葉を書きましょう。
頭語が「拝啓」であれば「敬具」、「謹啓」であれば「謹言」や「敬白」を使います。
後付け
後付けとは、いつ誰が誰に宛てて書いた手紙なのかを明らかにする役割を持つものです。結語の後に、日付、氏名、宛名を書きましょう。
園全体に向けて送る場合は、宛名を「〇〇保育園の皆様」とするとよいかもしれません。
【相手別】保育実習や幼稚園実習のお礼状の例文
 west_photo / stock.adobe.com
west_photo / stock.adobe.com
お礼状の基本的な書き方押さえたうえで、ここでは、園長や複数の保育士さんなど宛先別にお礼状の例文を紹介します。また、幼稚園実習のお礼状を書く際は、幼稚園の先生向けに文章を記載しましょう。
園長先生に宛てた例文
園長先生を宛名とした場合の例文です。
謹啓
早春の候、皆様いかがお過ごしでしょうか。
この度は、お忙しい中14日間にわたり保育実習の機会を与えていただき、誠にありがとうございました。
初めての責任実習ということで準備を重ねて挑んだものの、計画通りにはいかないのが保育の現場であることを痛感いたしました。その場で子どもたちの様子を見て、時には活動を変えていくといった臨機応変な対応が求められることを学びました。
また、子どもたちの動きを想定しいくつか案を練っておくことも大切であると教えていただき、自分自身の課題を見つけることができたと感じております。
この度の保育実習で学んだことを胸に刻み、一人前の保育士になるため精進して参ります。
末筆ではございますが、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。
敬白
令和〇年〇月〇日(書いた日の日付)
〇〇大学(短期大学、専門学校)〇〇科 〇年
〇〇〇〇(自身の名前)
〇〇保育園(幼稚園) 園長〇〇〇〇様
園の職員さん全員に向けた例文
宛名を「職員の皆様」とした場合の例文です。
拝啓
深緑の候、皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
この度は14日間にわたり保育園実習をさせていただきまして、誠にありがとうございました。私にとって大変貴重な経験となりましたこと、心から感謝しております。
今回の責任実習を通して、複数担任でのクラスの進め方を学ぶことができました。
未満児クラスは発達の差が大きいことから、保育士同士で連携するために、報告・連絡・相談が欠かせないということを実感いたしました。
子どものためにさまざまな視点から考え援助している先生方の姿を拝見し、さらに勉学に励もうと思っております。
最後になりましたが、終始熱心にご指導くださいました園長先生をはじめ、諸先生方には感謝の気持ちで一杯です。本当にありがとうございました。
末筆ながら、皆様のご健康をお祈り申し上げます。
敬具
令和〇年〇月〇日(書いた日の日付)
〇〇大学(短期大学、専門学校)〇〇科 〇年
〇〇〇〇(自身の名前)
〇〇保育園(幼稚園) 園長〇〇〇〇様
職員のみなさま
指導担当の保育士さんに宛てた例文
指導担当をしてくれた保育士さんに宛てて送る場合の例文です。
謹啓
新秋の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
先日の保育園実習の折には、お忙しい中、2週間にわたり丁寧なご指導を賜りまして、誠にありがとうございました。◯◯先生は大変温かく指導してくださり、心から感謝しております。
今回の実習では0歳児から5歳児のクラスに入らせていただき、年齢による発達の違いと声のかけ方など対応のしかたの違いを知ることができました。また、0、1歳児は年齢だけでなく月齢や個人でも発達の違いが大きく、それぞれにあった対応をしていくことが大切だとわかりました。
短い期間ではありましたが、実習を通して保育士になりたいという思いがより一層増したように思います。これからも一人前の保育士になれるよう、努力してまいります。
末筆ではございますが、皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。
謹言
令和〇年〇月〇日(書いた日の日付)
〇〇大学(短期大学、専門学校)〇〇科 〇年
〇〇〇〇(自身の名前)
〇〇保育園(幼稚園) 園長〇〇〇〇様
〇〇〇〇先生
法人の担当者に宛てた例文
保育園を運営する法人の採用担当者を宛名にした場合の例文です。
謹啓
師走の候、皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
先日は大変お忙しいなか、保育実習を受け入れてくださりありがとうございました。
今回の実習では、先生方が行う子どもたちのやる気を引き出す工夫を随所で発見し、とても勉強になりました。
声のかけ方や言い方を少し変えるだけで子どもたちの興味が違う方向へと向き、先生方がスムーズに活動に入られているのを見て、声かけの重要性を改めて感じる機会となりました。
3週間という短い期間ではございましたが、経験が豊富な先生方と保育現場に立つことができ、保育士になりたいという気持ちがより一層強まったと感じております。
末筆ではございますが、今後の皆様のご活躍とご多幸をお祈り申し上げます。
敬白
令和〇年〇月〇日(書いた日の日付)
〇〇大学(短期大学、専門学校)〇〇科 〇年
〇〇〇〇(自身の名前)
〇〇法人 〇〇保育園(幼稚園)
人事部人事担当 〇〇〇〇様
宛先が誰であっても、基本的な文構成は同じになります。
園長先生や法人の担当者に宛てて書く場合でも相手を限定せず、「先生方」「園の皆様」といった形で表現しましょう。
保育実習や幼稚園実習のお礼状を書くときのポイント
保育実習を機に初めてお礼状を書くという方も少なくないかもしれません。
ここでは、お礼状を作成するときに意識したいポイントを紹介します。
マナーを心がける
お礼状は改まった手紙であるため、書き方の構成やマナーを押さえて作成しましょう。
なかには書き方がわからず自己流で書いてしまうという方もいるかもしれません。
お礼状は感謝の気持ちを伝えるための手紙ではありますが、単にお礼を綴っているだけではマナーがないと思われてしまうおそれもあります。
頭語や時候の挨拶などきちんとした書式に則って作成してあることで、受け取り手に気持ちよく読んでもらえるでしょう。
学びや感想を具体的に記す
お礼状には、自分が実際に感じたことや気づきを書きましょう。
時候の挨拶や安否の挨拶など、形式に沿った書き方をする部分もありますが、学んだことやエピソードを自分の言葉で具体的に書くことで、より感謝が伝わりやすいお礼状となりそうです。
例文を参考に保育実習や幼稚園実習の感謝を伝えるお礼状を作成しよう
今回は、保育実習や幼稚園実習のお礼状の書き方や宛先別の例文を紹介しました。
実習後に送るお礼状は、形式的な書き方に沿って作成するのがマナーです。
頭語や時候の挨拶から始まり、結語や後付けで締めるという書式を守って書くことで、読み手に伝わりやすいお礼状となるでしょう。
また、3月なら早春の候、9月なら新秋の候など、1月から12月まで実習の季節にあわせた季語を用いることも大切です。
今回紹介した文を参考に、自分の学びや気づきを添えてより感謝の伝わるお礼状を作成してみてくださいね。
また、保育士バンク!新卒では、保育学生さんの実習や保育スキルを高めるための記事を配信しています。
就活のサポートもいたしますので「自分がどのような園で働き始めればよいのかわからない……」という方は、お気軽にご相談ください。