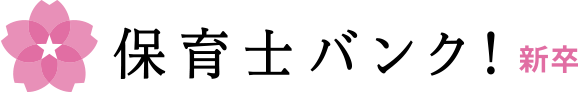6月30日に淑徳大学にて開催された、てぃ先生の特別講演会。
後編となる今回は、実際に保育現場で使うことができるテクニックや、
てぃ先生の考える「保育士だからこそできること」などについて講演の様子をご紹介します。

色んな園を見学して、後悔のない就活を!

ちょうど就活目前シーズンということもあり、てぃ先生からは、これから保育士を目指す学生への応援メッセージも。
「学生の皆さんはこれから就活が始まると思うのですが、保育業界の就活は一般企業とは違う風習があります。
一般企業では何十枚も履歴書を書いて複数の会社を受けるのに対し、保育士の場合は一園だけ受けて、高い確率で採用され、そのまま就職する。
その結果、自分に合わず離職してしまう保育士が多いんです。」
「古くからあるこの就活の体制は、問題だと思っています。インターネットで保育士の求人サイトを見ると、
多くの園が保育士を募集しているので、ぜひ色々な園を比較して、面接の前には必ず見学へ行くようにしてほしいです。
現場で働く側の人間としても、面接の時に初めてその園のことを知る、ということでは困ってしまいます。
どんな先生がいるかな?子どもたちの姿は?と視野を広げることで、後悔のない就活になると思うんです」
保育業界に浸透している就職活動の当たり前。
保育現場の問題を改善するためにも、まずは就活の方法から見直しが必要であるとてぃ先生は考えます。
また、保育士のキャリアの可能性について、てぃ先生はこのように考えます。
「僕は今後、自分の保育園を作りたいと思っています。
それに先立ち、来年からとある保育園で日本初となる『顧問保育士』という役職でお仕事をさせていただく予定です。
どのような立場かと言うと、企業の顧問弁護士のように、自分の保育の知識や経験を活かして、園経営の手助けをしたりします。
保育士のキャリアとして、現場で園長を目指すだけでなく、自分で考えて役職を作ることだってできるんです。
現場の保育以外にやりたいことがあれば、皆さんもぜひ挑戦してみてください」
保育のプロとして持つべき視点
「保育士って子どもと遊んでる仕事でしょ」残念ながら、世間からはそういった認識をされてしまうこともある保育の仕事。
では、保育士だからこそできるアプローチとは何でしょうか。子育てと保育の違いは?
「テーブルに登っている子どもがいたら、親御さんは『危ない!降りなさい』とすぐに注意するかもしれません。しかし保育士は、まず観察をするんです。
なんで彼はテーブルに乗っているんだろう?高いところに乗ったら良い景色が見えるから?テーブルの下に苦手な子がいたから逃げたのかな?と仮説を立ててアプローチします。
しかし、このアプローチがヒットしないことも多いので、僕はいつも『どうしたの?』と聞くようにしています。
すると彼は『ここに登ったら、先生と同じものが見えるから』と答えました。
もし僕が『すぐにテーブルから降りなさい』と彼を叱ったら、その言葉を聞けなくなってしまいます。
怪我に繋がる危ないことはすぐにやめさせなければいけませんが、『なぜ?』と考えた上でアプローチをすることが、保育であると思っています」
また、保育士の腕の見せ所は「スキマ時間」にあるとてぃ先生。
「保育の中で主活動を展開するのは、ある程度の経験を積めば誰でもうまくできるんです。
しかし、主活動と主活動の間のスキマ時間に上手なアプローチをするのは難しいんです。
ここが保育士の腕の見せ所だと思っています。
活動と活動の間の「待ち時間」を、いかに退屈させずに、フォローできるか。
そんな保育ができるといいですよね。
手遊びや素話もいいのですが、僕がよくやるのはみんなでお話を作っていく遊びです。
物語の大筋や最後のオチは先生が考えて、『王子様は街で誰に会ったのかな?』『お店で何を買ったのかな?』と、
子どもたちに投げかけながらお話を作っていくんです。
だいたい3歳以上になると楽しめる、おすすめの遊びです。」
講演中には、実習先で実際に使うことができる自己紹介の仕方や手遊びをレクチャーする場面も。
学生の皆さんたちからは「可愛い!」「実習でやってみます」と絶賛の声があがりました。
15年後の保育士のためにできること

「僕が見ている子どもたちの中にも、将来は先生みたいな保育士さんになりたい、と言っている子がいます。
皆さんは目の前にいる子どもたちに、保育士っていいよ、と勧められるでしょうか?
僕は、何とかしなければいけない課題が保育業界にはまだ残っていると感じています。」
「たとえば、保育業界には、スマホやタブレットを子どもたちに触れさせてはいけない、というような意見もあります。
でも、便利な道具をどう活用すれば良いのかを子どもたちに教えることが、僕たちの役割ではないでしょうか。
その子が将来にどう賢く生きていけるかを考えてアプローチをしなければ、保育業界はずっと、時代に取り残されたままになってしまいます。
それを変えていくのが、皆さんだと思います」

これから保育者を志す学生の皆さんに対し「心から応援します」とエールを送るてぃ先生。
最後には花束を貰い、全員で記念撮影を行いました。
講演の中で、てぃ先生は保育の仕事についてこのようにまとめています。
「子どもを見る仕事、という前に、ひとりの人間を見る仕事であることを忘れないでください」
就学前までの6年間だけを考えるのではなく、
子どもたちの人生全体を見て、ひとりの人間として向き合うこと。
てぃ先生の言葉は、これから保育の世界へ一歩を踏み出す学生たちにとって、
改めて保育の仕事を考えるきっかけとなったのではないでしょうか。
構成:佐藤愛美