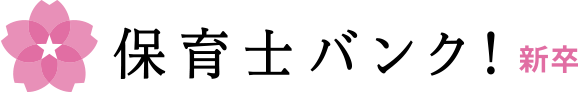保育学生さんの中には、就活の軸の決め方が分からない方もいるかもしれません。園選びの基準にしたり面接対策をしたりするためにも、しっかり見つけておくとよいでしょう。今回は、就活における軸の決め方や見つけ方をくわしく紹介します。あわせて、面接やエントリーシートで活かせる例文もまとめました。

hikdaigaku86/stock.adobe.com
■目次
保育士の就活における軸とは
就活において自分が仕事をしたり、志望する園を選んだりするときの基準を「就活の軸」と呼びます。
保育学生さんの場合は、入職する園に求める働き方や環境、保育理念といった条件が就活の軸と言えるでしょう。
まずは、就活の軸を「自分に関する軸」と「園や企業に関する軸」の2つに分けて、くわしく解説していきます。
自分に関する軸
自分が行いたい保育や、理想とする保育士像を実現するための条件は、自分に関する軸として考えられます。
例えば、異年齢の子ども同士のかかわりを学びたいと考えている方は「縦割り保育など異年齢で遊べるような環境を作っていること」を軸にするとよいかもしれません。
自分が保育を通して育みたい姿や学びたいスキルを挙げて、それらを実現できる保育環境をイメージしてみるとよさそうですね。
園や企業に関する軸
保育環境に求める条件を基準にする場合は、園に関する軸として考えられるでしょう。
例えば、一人暮らしをしたいと考えている方は、「家賃補助・引っ越し補助が支給されること」を軸にすることで、金銭面の負担を軽減することができそうですね。
他にも、事務作業より保育に時間をかけたい方は「事務作業のICT化を進めている」園を選ぶことで、じっくり子どもと向き合うことができるでしょう。
就活の軸を決めるメリット
ここからは、就活の軸を決めることのメリットについて見ていきます。
応募する園を選ぶのに役立つ
たくさんの園からぴったりの職場を探すのは時間がかかったり、探しているうちに自分の求める基準が分からなくなったりすることもあるでしょう。
しかし、自分の軸を決めておけば、就職の方向性がきちんと定まりそうです。
自分の軸に合った保育園をいくつか選んで比較検討もできるので、理想の職場を見つけやすくなるかもしれませんね。
面接の受け答えに活かせる
面接で準備をしていなかった質問をされたときも、就活の軸があると受け答えがしやすくなりそうです。
想定していない質問をされるとつい慌ててしまい、それまでに伝えた内容とずれた回答をしてしまう方もいるかもしれません。
就活の軸を中心に話すことで、いざというときも一貫性のある受け答えができるでしょう。
ES・履歴書を作成する際にも、就活の軸を中心に志望動機や自己PRを考えることで書きやすくなるでしょう。
また、実際に価値観や本気度を見るために、「就活の軸は何ですか?」と面接・書類などで聞かれることもあるようです。
そのため、面接対策などのためにも就活の軸を定めておくと安心かもしれませんね。
入職する園を決めやすくなる
就活の軸を定めるメリットとして、入職する園を決めやすくなるという点も挙げられそうです。
保育学生さんの中には複数の園から内定を頂き、どこへ入職するか悩む方もいるかもしれません。
そのようなとき、就活の軸を基準にして園を見定めれば、悔いのない判断をすることができるでしょう。
就活の軸を決めるときのポイント
続いて、就活の軸の決め方について紹介します。
自身の価値観を尊重する
就活の軸の決め方として、自身の価値観を尊重することが大切です。
「好印象を与えられそうだから」と本・インターネットに掲載されていた軸をそのまま使っても、自身に合うとは限らないでしょう。
弱い軸になって自分に合う園を選べなかったり、話の内容に一貫性がなくなったりすることが考えられます。
自分の気持ちに素直になって軸を作るとよさそうですね。
園の特徴を意識する
入職したい園は決まっているけれど、就活の軸が定まっていないということもあるかもしれません。
そのようなときは、園の特徴を踏まえて就活の軸を考えてみるのも一つの方法です。
例えば、入職したい園の特徴が小規模保育だった場合、小規模保育の特徴やメリットなどを調べます。そのうえで自分に合っているなと思ったら、「小規模保育を行っていること」を就活の軸にするとよいでしょう。
志望動機や面接などでは「一人ひとりに寄り添えるから」などの理由も添えれば、より説得力のある内容を伝えられそうです。
しかし、園の特徴に無理に寄せた軸を作った場合、入職後にミスマッチが起きてしまう可能性があります。
そのため、園の特徴だけではなく、自分の価値観も踏まえながら軸を作れるとよいですね。
ネガティブな内容は避ける
「休みが多い」「残業が少ない」のように、労働条件のみを重視した軸は、「保育に興味ないのかな」と採用担当者がマイナスのイメージを持たれてしまう可能性があります。
しかし、軸のひとつとしては重要なポイントなので、「休みが多い」⇒「ワークライフバランスを重視している園」など言い方に気をつけたり、そもそも待遇面に関した軸は避けたりするとよいですね。
具体的な表現を使う
就活の軸の決め方として、具体的な表現を使うのも大切でしょう。
「雰囲気のよい保育園」のように軸がぼんやりしていると、ESに書いたり採用担当者に伝えたりしたときに意味が分かりづらくなりそうです。
そのため、「保育士同士の連携が活発」など、客観的に分かりやすい具体的な軸を決めるとよいでしょう。
保育士の就活における軸の決め方

mapo/stock.adobe.com
いろいろ軸にしたいことはあるものの、どれにしようか決められない保育学生さんもいるでしょう。
そこで、就活の軸の決め方を具体的にまとめました。
1.自己分析を行う
自己分析とは、自分の長所や価値観について分析することを指します。
自己分析の方法としては、モチベーションが上がったエピソードや感情が動いた出来事などを書き出すとよさそうです。
いくつか書き出せば共通点に気づいてそれが軸になったり、「どのように働きたいか」「自分の得意なことは何か」に気づいたりできるかもしれませんね。
2.ノートに記入する
自己分析が終わったら保育士の仕事を通して実現したいことや、働きたい職場を理由といっしょに書いてみるとよさそうです。
ここでは、書き出しておくとよさそうな内容をそれぞれ解説します。
やりたいこと
保育の中でやりたい活動や、力を入れたいことを考えてみるとよいでしょう。
例えば、「絵をかくことやものづくりが好きなので、保育でもたくさん造形活動を行いたい」などと考えていくと具体的な条件が決まりそうですね。
働き方、保育理念
「子どもとこんな風にかかわっていきたい」という、自分の保育観も大切な条件となりそうです。
例えば、「一人ひとりと丁寧にかかわれる保育がしたい」と考えている場合、同じような保育理念を掲げている園を探すとよいかもしれません。
仕事をする環境
いっしょに働く同僚や、園の設備などの職場環境を条件にすることもできるでしょう。
「広々とした空間でのびのびと保育がしたい」という方は、大規模な園舎のある園や遊戯室・プレイルームなどの部屋が充実している園を選ぶとよさそうです。
自分ができること
自分のできることや能力から、そのスキルを活かせそうな職場の条件を見つけることもできるでしょう。
得意なことや人から褒められたことを考えてみたり、これまでの経験から思い出したりすることで、自分の能力を発見できるかもしれません。
「植物の種類に詳しくお世話が得意だ」という方は、園庭で畑づくりを行っていたり自然環境を充実させていたりする園を選ぶなど、自分のできることを活かしていけるでしょう。
3.優先順位をつける
自分に合った条件をもとに就活の軸を考えることができたら、それぞれに優先順位をつけていくとよいでしょう。
優先順位をつけることで、似た条件の園で迷ったときに判断材料として活用できるかもしれません。
また、面接やエントリーシートで就活の軸を聞かれたときは、優先順位が一番高いものを回答するとよさそうです。
関連記事:自己分析の目的とやり方。ノートを使った方法や志望動機の例文/保育士就活バンク!
保育士の就活における軸の答え方・例文
保育園の面接では、「就活の軸は何ですか?」と聞かれることもあるかもしれません。
ここでは、就活の軸に関する質問があった場合の、保育学生さんの答え方例を解説します。
労働条件に関すること
まずは、労働条件に関する就活の軸の答え方を見ていきましょう。
保育規模が軸の場合
私の就活の軸は「小規模保育を実施していること」です。
子どもとの愛着関係を形成していくうえで、一人ひとりとじっくりかかわることのできる環境が望ましいと考えています。
丁寧なかかわりを持つことで子どもへの理解を深め、安心して過ごせる環境を作っていく保育を目標としています。
保育規模の軸として、「小規模保育を実施していること」を挙げている例文です。
「1人ひとりと丁寧にかかわって愛着関係を形成していきたい」のように、理由も添えることで具体的な文章に仕上がるでしょう。
福利厚生や育休制度が軸の場合
私の就活の軸は「長く働き続けられる環境」です。
子どもたちの成長を長く見守っていくためにも、自分自身が働き続けられる環境に身を置きたいと考えています。
長い目で保育を見通し、子どもとの時間を重ねていくことで、子どもに寄り添った保育ができればと存じます。
福利厚生や育休制度の軸として、「長く働き続けられる環境」を挙げている例文です。
「育休制度がある」のように直接的に伝えず、「働き続けられる環境で子どもと時間を重ねたい」のように説明すれば、ポジティブなイメージを与えられるでしょう。
自分のキャリアアップに関すること
続いて、自分のキャリアアップに関する就活の軸の答え方例を見ていきます。
自身の成長が軸の場合
私の就活の軸は「自己成長できる環境」です。
子どもにさまざまなことを学んでもらうためにも、自分自身が学び続ける必要があると考えています。
先輩保育士の姿から学ぶことはもちろん、園内研修に積極的に参加することで成長していきます。
自身の成長の軸として、「自己成長できる環境」を挙げている例文です。
「子どもが学ぶには、自分自身が学び続けなくてはいけない」のように、理由を添えると採用担当者も納得しやすくなるでしょう。
教育方針が軸の場合
私の就活の軸は「モンテッソーリ教育を行っていること」です。
将来的にしっかりと自立できるように、生き抜く力を育てられる保育士でありたく思っております。
モンテッソーリ教育を通して、社会を生きるうえで大切な自立性や忍耐力などを育んでいきたいと考えています。
教育方針の軸として、「モンテッソーリ教育を行っていること」を挙げた例文です。
「自立性や忍耐力を育みたい」のように目標も伝えれば、説得力のある文章に仕上がるかもしれませんね。
職場環境に関すること
最後は、職場環境に関する就活の軸の答え方例について見ていきましょう。
通いやすさが軸の場合
私の就活の軸は「地域貢献ができること」です。
幼い頃から地域の方々に温かく囲まれて育ててもらったことへの感謝の気持ちを糧に、自分がこの地域で育つ子どもの心を豊かなものにしていきたいと考えています。
保育を通して、自分が生まれ育った地域に恩返しをすることが目標です。
「地域貢献ができること」を軸として挙げた例文です。
「通いやすいから」などと伝えてしまうとネガティブな印象を与える可能性があるので、「自分が生まれ育った地域に恩返ししたい」のように言いかえるとよいでしょう。
人間関係が軸の場合
私の就活の軸は、「保育士同士が連携して保育できる環境」です。
保育園での実習を通して、保育士同士が協力しあって保育を行うことの重要性を学びました。
活動内容や子どもへのかかわりについて保育士同士で丁寧に話し合い、協力しながら質の高い保育を実現していきたいと考えています。
「保育士同士が連携できる環境」を軸として挙げた例文です。
「人間関係がよい」と伝えてしまうと軸として弱いため、例のように「保育士同士が協力し合える」など具体的に答えるとよいでしょう。
また、「保育園での実習を通して学んだ」のように、具体的なエピソードもいっしょに答えられるとよさそうですね。
就活の軸がない場合の見つけ方

oka/stock.adobe.com
自分が就活の軸にしたいことのイメージが浮かばない、何を軸にしてよいかわからないという方もいるのではないでしょうか。
そういった保育学生さん向けに、最後は、就活の軸の見つけ方を紹介します。
OB・OG訪問をする
就活の軸がない場合の見つけ方として、OB・OG訪問をすることが挙げられるでしょう。
OBやOGは就職の経験者なので、軸の決め方を教えてもらえるかもしれません。
また、エントリーシートや履歴書などを添削してもらい、アドバイスを頂くこともできそうですね。
いろいろな園を見る
いろいろな園を訪問したり説明会に参加したりすることで、就活の軸を決めることができそうです。
多様な園を見ていくうちに、自身が魅力を持つポイントに気づけるかもしれません。
また、2つの園を比べて「働くならこちらがよいな」と決めていく、2社比較というやり方も効果があるでしょう。
ネガティブな軸から考える
苦手なことや避けたい職場をイメージすることで、それらとは逆の園を探すという方法もあるでしょう。
製作が苦手という方は、「壁面装飾や造形活動を重視していないこと」を軸にすることで働きやすい園が見つかりそうですね。
例を参考にする
就活の軸がない場合の見つけ方として、例を参考にすることが挙げられるでしょう。
例えば、以下のような軸をもとに考えてみるとよさそうです。
- 1人ひとりの子どもと深くかかわりたい
- 子どもの自主性を尊重したい
- 運動を通して関係性を深めたい
- 保育のスキルを高めたい
- 長く働き続けたい
しかし、例をそのまま使ってしまうと自身の価値観に合わない可能性があるため、適宜アレンジしてみるとよいかもしれませんね。
関連記事:【徹底解説】園見学の流れとポイント。質問や挨拶の例文、服装や持ち物、電話やお礼状マナー/保育士就活バンク!
就活の軸の決め方を覚え、保育士の就活に役立てよう
今回は就活の軸の決め方や、ない場合の見つけ方について紹介しました。
就活の軸を決めることで職場選びがしやすくなったり、面接対策や内定後の判断に役立ったりするなどのメリットがあるようです。
しかし、軸が弱いと入職後に園とのミスマッチが起きるかもしれないため、理想の保育を考える、自分に合った働き方を明確にするなどしてしっかり決めるようにしましょう。
保育学生さんはここで紹介した答え方・例文などを参考に、自分に合った軸を定めて就活に活かせるとよいですね。
保育士就活バンク!は保育学生さんの就活を支援する求人紹介サービスです。
「自己分析がうまくいかない」「自分に合った求人を見つけられない」といった保育学生さんの悩みをアドバイザーがしっかり解消いたします。
一人の就活に不安のある方は、ぜひ保育士就活バンク!に登録してみてくださいね。