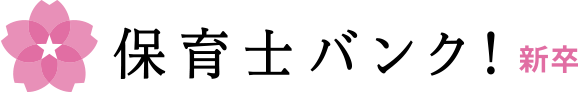保育士の住居にかかる費用を法人または国や自治体が負担する、社宅借り上げ制度。保育学生さんの中には、社宅借り上げ制度の内容を把握して就活に活かしたいと考える方もいるかもしれません。今回は、保育士にとっての社宅借り上げ制度とは何かや住宅手当との違い、利用するときの注意点、メリットとデメリットを紹介します。
 amasan / stock.adobe.com
amasan / stock.adobe.com
保育士にとっての社宅借り上げ制度とは
そもそも借り上げ社宅とは、法人が自社社員を住まわせるために契約している物件のことをいいます。企業側が社宅の家賃の一部を社員から徴収することで、低価格で住居を確保できる福利厚生の一つです。
保育業界における社宅借り上げ制度には、「保育事業者宿舎借り上げ支援事業」という独自の制度もあります。保育士人材の確保・定着・離職防止を目的とする、国や自治体が保育士さんの住宅費用を補助する取り組みです。
保育事業者宿舎借り上げ支援事業の場合、補助金を支払うのは国や自治体となります。そのため、補助を受けて実施している場合には、同じ法人の園でも所在地の自治体によっては行っていないことがあるので注意が必要です。
ただし補助金を受け取れるのは、あくまで物件を契約している園です。
毎月の給与とは別に、保育士さんが住む住居の家賃の補助として法人から直接支給される「住宅手当」として支払われるわけではないため、その点には注意しましょう。
就活無料相談保育士の社宅借り上げ制度と住宅手当の違い
では、保育士にとっての社宅借り上げ制度と住宅手当には、どのような違いがあるのでしょうか。それぞれの特徴を紹介します。
社宅借り上げ制度
借り上げ社宅の家賃は給与から天引きされます。物件の大家さんや仲介業者とのお金のやり取り、国や自治体との手続きは、法人が行うので保育士さんが直接かかわることはありません。
税の扱いなどの細かな条件は園の規程と法令に基づくため、確認してみるとよいでしょう。
住宅手当
住宅手当は、法人から職員に支払われる給与に含まれます。
賃貸や持ち家に住んでいる社員を補助する目的として支給される福利厚生の一つです。
住宅手当は給与にカウントされるため、その分の所得税を払わなくてはなりません。また契約金や家賃の支払いなどのお金のやり取りは賃貸契約者である保育士さん自身が行うことになります。
このように、保育士の社宅借り上げ制度と住宅手当には、補助のされ方やお金のやりとりに違いがあるようです。しかしどちらも住宅費用を法人が補助する制度という点では、同じような役割を果たしているといえるでしょう。
保育士の社宅借り上げ制度を利用するときの注意点
実際に保育士の社宅借り上げを利用したいと考えるとき、どのような点に注意が必要なのでしょうか。
対象となる勤務年数・利用回数を確認する
- 対象となる勤務年数
以前は段階的に対象保育士の勤務年数が短縮されていましたが、2025年度からは「採用された日から起算して5年以内」 とされています。 - 利用回数
自治体によっては原則として 「1人につき1回限り」 の利用制限を設けている場合があるようです。
この制度を利用して転職した場合、新しい職場では利用できない可能性があるため注意が必要です。 - 月額補助
上限7万5000円が目安となっています(2026年1月時点)
制度の適用条件は今後も変わる可能性があるため、必ず希望する保育園やその園がある自治体の窓口にご確認ください。
いつまで補助されるのか期間を確認する
自治体によっては保育士宿舎借り上げ支援事業の実施期間を違いがある場合があります。
保育人材の確保を目的とした施策ですが、財源確保などの問題が生じた場合、補助の規模を徐々に縮小していく可能性も考えられるでしょう。
具体的に補助の保証期間をいつまでとするといった共通基準がないため、制度を利用したい場合にはその自治体にあらかじめ確認しておき、計画的な住居選びや貯蓄を行なったほうがよいかもしれません。
同棲や結婚などの制限の有無を確認する
同棲や結婚などにより同居している場合を補助の対象外としている市区町村はあまりないようですが、保育園が独自で制限をかけている場合があります。
単身者のみの支給やパートナーが住宅補助を受けている場合、保育士さん側には手当が出ないといった条件を設けている園もあるため注意が必要です。
保育士の社宅借り上げ制度を利用できるかは最終的には保育園を運営している事業者次第となるため、しっかりと補助の内容を確認したうえで、自分に合った制度を設けた園に応募するのがよさそうです。
保育士バンク!新卒に宿舎借り上げ制度を利用できる園を探してもらう
保育士の社宅借り上げ制度を利用するメリットとデメリット
 rrice / stock.adobe.com
rrice / stock.adobe.com
最後に、保育士の社宅借り上げ制度を利用するにあたってのメリットとデメリットを紹介します。
メリット
保育士の社宅借り上げ制度には、以下のようなメリットが挙げられるでしょう。
- 入職や転勤時に住宅を探す必要がなく、引っ越しが必要な際の負担が軽減される
- 賃貸契約手続きや家賃支払い処理も不要になる
- 賃貸契約の更新料なども発生しない
- 給与から家賃が引かれれば、所得額が減るため節税につながる
- 給与が増えても借り上げ社宅に伴う増税負担はない
給与が増えるほど税収も上がってしまう住宅手当とは異なり、税負担が増えないことや昇給しても社会保険料の支払額が変わらないというメリットは魅力的といえるでしょう。
また園によって社宅物件を複数契約している場合、規定の範囲内で好きな社宅を選ぶこともできるようです。住所が固定されてしまう社員寮などよりは自由度が高いかもしれません。
デメリット
保育士の社宅借り上げ制度を利用する場合のデメリットとしては以下のようなことが挙げられるでしょう。
- 所定物件のため、好みの物件や場所を自由に選ぶことはできない
- 所得額が減ることで社会保障額が減る可能性がある
- 入居可能年数に期限がある場合がある
上述の通り、住宅手当と比べて物件の選択肢が少ないのが借り上げ社宅のデメリットといえそうです。住みたい地域や理想の間取りを固定しすぎると、希望が叶えられない可能性もあるので注意が必要です。
また、借り上げ社宅には法人によって入居期限が設けられている場合があり、それを超過する場合は退去しなくてはなりません。いつまで住めるのか、あらかじめ法人や園に確かめておくとよいでしょう。
以上のようなメリット・デメリットを把握しておけば、就活で施設情報を見るときにも役立つかもしれません。
保育学生さん自身の住居に関して、譲れるポイントと譲れないポイントを照らしあわせて、保育士の社宅借り上げ制度を利用したいかどうかから考えるとよさそうです。
出典: 令和年度7年度保育関係予算案の概要/こども家庭保育士の「借り上げ社宅制度」よくある質問Q&A
一人暮らしを考えている保育学生さんにとって、最大7万5,000円(※地域による)などの家賃補助が出る「借り上げ社宅制度」は魅力的ですよね。
しかし、「家は自由に選べるの?」「お金は本当にかからないの?」と気になることも多いはず。
ここでは、借り上げ社宅制度に関するよくある疑問をまとめました。
Q. 住む物件は自分で自由に探せますか?
園が提携している不動産会社の中から好きな部屋を選べる「選択型」と、園が所有・契約しているマンションに入居する「指定型(寮タイプ)」の2パターンがあるようですが、指定されることが多く、自分で選ぶことは難しいでしょう。
Q. 恋人との同棲や友人とルームシェアは可能ですか?
借り上げ社宅制度は、自治体からの補助金で運営されているため、基本的には「保育士本人の住まい」であることが条件となり、同居は認められないケースがほとんどです。ただし、結婚した場合に世帯主であればOKとする園や、同居人の分は自己負担すればOKとする園も稀にあるため、規定を確認してみるとよいですね。
Q. 「家賃無料」といっても、初期費用や管理費はかかりますか?
多くの園では「家賃(賃料)」は全額補助されますが、毎月かかる「管理費・共益費(数千円~1万円程度)」は自己負担となることが一般的です。また、敷金・礼金は園が出してくれることが多いですが、引越し業者代や家具家電の購入費は自分で用意する必要があるため、ある程度の貯金は必要です。
保育士の社宅借り上げ制度の内容を把握して就活を進めよう
今回は、保育士の社宅借り上げ制度とは何かや住宅手当との違い、利用するときの注意点、メリットとデメリットについて紹介しました。
「保育士宿舎借り上げ支援事業」を含む保育士の借り上げ社宅制度は自治体や法人によって取り入れているかどうかが異なるようです。
また、いつまで入居できるかや結婚に関する条件などについても、それぞれの園によって規定が異なるかもしれません。
保育士の社宅借り上げ制度を利用したい場合は、制度の内容をよく把握して、自身が勤めたいと思う保育園の求人情報も調べながら就活を進められるとよいですね。
保育士バンク!新卒では、社宅借り上げ制度を利用できる園のご紹介をしていますので、お気軽にご相談ください。