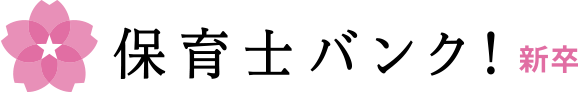昔から親しまれるあやとり遊び。室内遊びに取り入れやすいため、保育活動で計画したい保育学生さんや新卒保育士さんもいるでしょう。ほうきなどひとりで作る定番ネタのほかにも、もちつきやのこぎりといったふたりでの遊び方を覚えておくと役立ちそうですね。今回は、子どもでも簡単にできるあやとり遊びをジャンル別にまとめました。

KPG_Mega/shutterstock.com
あやとり遊びとは?
あやとり遊びの概要
あやとりは、わっか状に結んだ毛糸を指にかけてとり、さまざまな形を作って楽しむ遊びです。
日本で昔から親しまれてきた伝承遊びの一つのため長い歴史があり、たくさんの技や作り方が残されています。
保育園でも、毛糸をわっかにして結ぶだけで簡単に作れるので、手軽に取り入れることが可能です。
自由遊びや延長保育の時間にぴったりな遊びですが、子どもたちが糸で首を締めることがないよう、注意して見守ることが大切になるでしょう。
あやとり遊びで期待できる効果
- 指先を使って糸を取ることで手先の器用さを育む
- あやとり遊びを再現することで記憶力や創造性を高める
- 技を成功させて達成感や自信につながる
子どもが楽しみながら指先の巧緻性や想像力を高めていけるように、遊びのなかで援助していきましょう。
子どもたちの興味やレベルに合わせた技を楽しむことで、より意欲を育んでいけそうですね。
【ひとり編】定番のあやとり遊びのやり方
まずは、ひとりで楽しめるあやとり遊びのやり方についてみていきましょう。初心者向け・中級者向け・上級者向けとレベル別に紹介します。
ひとりあやとり遊び:初心者向け
あやとり遊び初心者の子どもでも楽しめそうな簡単なやり方を練習してみましょう。
ほうきの作り方
完成するときに、パンと手を叩いて開くとほうきが作れるため、パンパンほうきとも呼ばれているようです。
まるで手品のような作り方なので、初めてあやとり遊びを教えるときに披露すると、子どもたちも関心を持ってくれるかもしれませんよ。(詳しい説明はこちら)
2本ほうきの作り方
両手にほうきを作ることができるユニークな遊び方です。1本のほうきが作れるようになったら挑戦してみましょう。
糸をまとめて持つ部分があるので、ゆっくりと行ってみてくださいね。
ちょうちょの作り方
小指を使ったり、手首を返したりと少し難しい工程がある作り方です。
指から糸が外れないように、「気をつけてね」と声をかけながら作ってみましょう。
ひとりあやとりの定番な作り方のひとつなので、あやとりに慣れるための一歩として行ってもよさそうです。(詳しい説明はこちら)
つづみの作り方
立体的に糸が交差する様子が面白く、簡単な作り方でも達成感を味わえるつづみの作り方です。
最初の構えで手首に糸を巻きつけるのにつまずく子どももいるかもしれないため、側で見本を見せながら行うとよさそうですね。
かえるの作り方
糸を指から外す工程がいくつかあり、初心者向けの作り方のなかでも少し難しいかもしれません。
外す糸をしっかり確認しながら、ゆっくりと実践してみるとスムーズに作れるでしょう。
おみくじの作り方
糸を引っ張っておみくじをして楽しめる、特別なあやとり遊びです。
保育学生さんがおみくじを作れば、子どもたちは糸を引いて簡単に遊ぶことができます。
あやとり遊びに興味を持ち始めた子どもたちといっしょに楽しんでみてくださいね。
ひとりあやとり遊び:中級者向け
ここでは、あやとり遊びに慣れてきていろいろな作り方に挑戦したい子どもたち向けに、中級レベルの遊び方を紹介します。
ゴムの作り方
完成したあとに、引っ張ったりゆるめたりしてゴムのように伸び縮みさせて遊ぶことができる楽しいあやとり遊びです。
小指でたくさんの糸をとるのにはコツが必要なため、扱いやすい糸でゆっくりと挑戦してみましょう。
せんすの作り方
最初の構えが少し複雑ですが、原型を作れば簡単に遊ぶことができるせんすの作り方に挑戦してみましょう。
右手と左手で非対称になるため、子どもに作り方を説明するときは対面ではなく、横並びになって教えることがポイントと言えそうです。
かにの作り方
重なる糸が多く、手首をひねりながら糸をとるなど、難しい部分のあるかにに挑戦してみましょう。
糸を外す部分では、ほかの指から糸が抜けないように気をつけてみてくださいね。
富士山の作り方
富士山は、他の指を使って糸を外したり、糸をひねったりする少しやり方が難しいあやとり遊びです。
外す糸を間違えないよう、しっかりと確認しながら行うと成功しやすいかもしれません。
1段はしごの作り方
はしごには1段だけでなく、2段、3段とたくさんの形があります。
最初の形となる1段はしごですが、ちょうちょやほうきよりもやや難しい作り方なので、あやとりに慣れたらチャレンジしてみましょう。
指から糸を外すところでは、保育学生さんが外す糸を確認しながら見守るとよさそうですね。(詳しい説明はこちら)
2段はしごの作り方
2段はしごではより複雑な工程になっています。
保育学生さんが子どもといっしょに作りながらやり方を確認するようにしましょう。
まずは保育学生さんがお手本を見せて、そのあと子どもといっしょに作っていくとよいかもしれません。(詳しい説明はこちら)
ひとりあやとり遊び:上級者向け
最後に、あやとり遊び上級者向けの難しい作り方をまとめました。
かめの作り方
少し難易度の高いかめの作り方に挑戦してみましょう。
糸同士が重なり合うためとるべき糸がわかりにくくなりますが、動画と照らし合わせながら繰り返し練習することが大切になりそうです。
3段はしごの作り方
3段はしごでは、狭い隙間を通るなど、とるべき糸がわかりにくい工程が多いようです。
動画を見ながら少しずつ進めてみてくださいね。
子どもに教えるときには、一つひとつの工程をゆっくり確認しながら、根気強く挑戦してみましょう。(詳しい説明はこちら)
4段はしごの作り方
多段はしごの最後の形、4段はしごです。
段が増えて作り方も複雑になっていますが、工程ごとにとる糸や外す糸を確認しながら、ゆっくり練習することが大切になるでしょう。
難しい分、完成したら大きな達成感が味わえるかもしれません。できたときは保育学生さんがたくさん褒めるとよさそうですね。(詳しい説明はこちら)
東京タワーの作り方
東京タワーは、前述した4段はしごを応用して作れる形です。
ひとつの形の作り方をマスターすれば、他の形にも発展させられる面白い作り方ですね。
あっという間に次の形ができる様子に、子どもたちもびっくりしてくれるかもしれません。
トンネルの作り方
トンネルも東京タワーと同じく、4段はしごからアレンジできる遊び方です。
小指を使って糸をとるのが難しいですが、他の糸が指から外れないように注意しながら挑戦してみましょう。
以上のように、ひとりでのあやとりの遊び方には、簡単な定番の技から難しい作り方までさまざまあります。
子どもに教えるときは、お手本を見ながら少しずつ挑戦できるよう援助しましょう。
【ふたり編】定番のあやとり遊びのやり方
ふたりでできるあやとり遊びでは、1本のあやとりをふたりでいっしょに使って遊ぶことができます。
ふたりで同時に糸を使うやり方、交互に糸をとるやり方があるため、まずは同時に糸を使う遊び方をみていきましょう。
ヤシの木の作り方
ひとりが糸を引っ張ってヤシの木の幹を表現する作り方です。
引っ張る役を子どもにお願いすれば、あやとり遊びが苦手な子どもでも技を完成できたよろこびを味わえそうですね。
もちつきの作り方
ふたりで同時に糸を使って遊べる、もちつきのやり方を紹介します。
作り方
1.ふたりで向かい合い、お互いにあやとりの糸を両手の親指と小指にかけます。
2.右手の中指で、相手の右手の平にかかっている糸をとります。
3.(2)と同様に左手の中指で、相手の左手の平にかかっている糸をとります。
4.ふたりとも(2)(3)で中指にかけた糸を残し、(1)の親指、小指にかけた糸を外します。
5.糸が十字になるようお互いにゆっくり引っ張ればできあがりです。
もちつきの形が作れたら、ふたりの手のひらを合わせて「ぺったんぺったん」ともちつき遊びをしてみましょう。
ポイント
ふたりでふれあいを楽しみながら遊べるもちつきの作り方です。 簡単に作れるので、子どもたちといっしょに遊んでみましょう。
もちつき遊びをするときには、合わせていない方の手で糸を引っ張るようにするとよいでしょう。
保育学生さんは、子どもの手をそっと持つなどして援助するとよいかもしれません。
のこぎりの作り方
のこぎりもふたりで同時に糸を使う遊び方です。くわしい作り方をみてみましょう。
作り方
1.Aさんは糸を両方の手首に一周させて巻きつけます。
2.右手の親指で左手の手首に巻きついている糸をとります。
3.同様に左手の親指で右手の手首に巻きついている糸をとります。
4.次に、BさんはAさんの手首にかかっている一番下の糸を両手で握ります。
5.Bさんはそのまま外側に引っ張ります。
6.Aさんも親指に残った糸を握りながら外側に引っ張ります。
7.糸が十字になるようにお互い引っ張ればできあがりです。
糸を交差させるように引っ張り、のこぎりを引いて遊んでみましょう。
ポイント
ふたりで息を合わせてぎこぎこと引く様子を楽しめるのこぎりのあやとり遊びです。
AさんよりBさんの工程のほうが簡単なので、まずは子どもにBさん役をお願いして教えるとよいかもしれません。
ふたりであやとり遊びをするときには、ひとりのときよりも長めのあやとりを使うとやりやすくなりそうです。
連続技のやり方
連続技では、ふたりが交互に糸をとりながら作品を完成させていきます。
ここでは、定番の遊び方として親しまれる連続技のやり方をみていきましょう。
どの形から作っても始められるので、動画を見ながら遊んでみてくださいね。
つりばしの作り方
つりばしは、連続技の最初の型となる作り方です。
手首にひもを一周巻きつけるため、保育学生さんがお手本を見せて作ってみるとよいでしょう。
田んぼの作り方
つりばしからスタートします。
1.クロス状にかかっている糸の交差部分を、側面から人差し指と親指で横に挟むようにつまみます。
2.そのままつまんで外側に引っ張り、手首にかかっている下の糸の内側を通って下からすくいあげます。
3.指を開いてできあがりです。
相手が作った「つりばし」の完成形から糸をとって作る遊び方です。
すくいあげる糸を間違えないよう、確認しながら遊んでみましょう。
一人の場合の「田んぼ」の作り方も動画になっているので、挑戦してみてくださいね。
関連動画:あやとりで簡単「田んぼ」の作り方【音声解説つき】初心者向け/保育士バンク!
川の作り方
田んぼからスタートします。
1.親指と人差し指にクロス状にかかっている糸を、上から垂直方向につまみます。
2.そのままつまんで上に引っ張り、下の糸の内側を通って下からすくいあげます。
3.指を開いてできあがりです。
重なりあっていた糸がほどけて川になる様子が面白いあやとり遊びです。
「川」からもさまざまな作り方に変形させられるため、マスターしておくと楽しいかもしれません。
一人の場合の「川」の作り方も動画になっているので、挑戦してみてくださいね。
関連動画:あやとりで簡単「川」の作り方【音声解説つき】初心者向け/保育士バンク!
船の作り方
船のやり方は、川の完成形からスタートします。
1.真ん中にある2本の糸を、交差させるように両手の小指を使ってとります。
2.そのまま横に引っ張ります。
3.人差し指と親指を使って、下の糸の内側を通って下からすくいあげます。
4.指を開いてできあがりです。
連続技では、自分の番で必ずひとつの技が完成するため、上手にできれば達成感を得られるでしょう。
一度作り方を間違えると技が途切れてしまうため、慣れないうちは保育学生さんが確認しながらいっしょに遊ぶとよいかもしれません。
このようにふたりあやとりには、友だちや先生とふれあいながら楽しめるやり方や、次々と展開していく連続技など面白い作り方がさまざまあるので挑戦してみてくださいね。
簡単なあやとり遊びを知って、保育園でやってみよう
今回は、保育園で楽しめる簡単なあやとり遊びを紹介しました。
ひとりでできる遊び方には、ほうきやちょうちょなど定番の遊びの他にも2段、3段……とバリエーション豊富なはしごの作り方などがあります。
ふたりあやとりでは、ふれあいを楽しめるもちつきや、どんどん形が変わる連続技などユニークな遊び方がたくさん存在します。
指先の動きや思考力の発達にも役立つあやとり遊びを、ぜひ保育園の子どもと楽しんでみてくださいね。