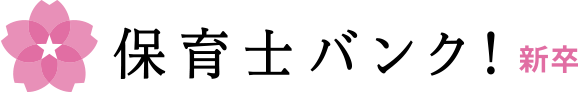2025年3月20日(木)の「春分の日」とはどのような由来、意味があるのでしょうか。日付が毎年違うため、その理由も気になりますよね。今回は、春分の日についてわかりやすく解説します。子ども向けの簡単な伝え方や活動アイデアも紹介するので、新卒の保育士さんは参考にしてみてくださいね。
 KAI / stock.adobe.com
KAI / stock.adobe.com
春分の日とは。毎年違うのはなぜ?
春分の日は、毎年3月20日〜21日ごろに設定される国民の祝日です。
2025年は3月20日(木)です。
春分の日は毎年同じ日ではなく、年によって変わります。
これは、太陽が「春分点」を通過する瞬間がいつになるかを計算して日付を決定するためです。
そもそも、地球が太陽のまわりを回る周期は「365日ぴったり」ではなく、約365.24日かかります。
しかし、私たちが使っているカレンダー(グレゴリオ暦)では1年を365日と定めていることから、少しずつズレが生じます。
このズレを調整するために、4年に一度「うるう年」(366日)を設けていますが、その影響で春分の日も毎年変わることがあります。
こうした天文学的な計算に基づき、春分の日は毎年3月20日または21日に決められます。
春分の日の由来や意味
春分の日の由来
春分の日の由来は、「春季皇霊祭(しゅんきこうれいさい)」という宮中行事にさかのぼります。
「春季皇霊祭」は1878年(明治11年)に制定され、現在も天皇家の祖先をまつる儀式として宮中で執り行われています。
その後、戦後の1948年(昭和23年)に「国民の祝日」として「春分の日」が制定されました。これにより、皇室の祭祀だった「春季皇霊祭」は、一般の国民にとっても馴染みのある祝日へと変わったそうです。
春分の日の意味
 tilly / stock.adobe.com
tilly / stock.adobe.com
春分の日は「自然をたたえ、生物をいつくしむ日」「お彼岸の中日」として2つの意味があるといわれています。
自然をたたえ、生物をいつくしむ日
春分の日は、「自然をたたえ、生き物をいつくしむ日」として定められた国民の祝日です。
また、春分は二十四節気(にじゅうしせっき)のひとつで、季節の移り変わりを知らせる重要な日とされています。
この日を境に昼と夜の長さがほぼ等しくなり、本格的な春の訪れを感じる頃となります。
昔からこの時期は、自然の恵みに感謝し、新たな季節の始まりを祝う節目として大切にされてきたようです。
そのため、春分の時期は農作業を本格的に始める目安とされ、種まきや田畑の準備に適した時期とされてきました。
「お彼岸の中日」
春分の日は、「お彼岸の中日(ちゅうにち)」にあたり、ご先祖様を供養する日といわれています。
「お彼岸」とは、春分の日や秋分の日を中日とした前後3日間、合計7日間のことです。
春分の日は太陽が真東から昇り、真西に沈むため、彼岸(あの世)と此岸(この世)が最も近づく日と考えられてきました。
そのため、お墓参りをしたり、仏壇にお供えをしたりする風習が広まったそうです。
春分の日には「ぼたもち」秋分の日は「おはぎ」を食べる理由
春分の日と同様に、秋分の日も国民の祝日です。秋分の日は毎年9月23日頃にあたり、昼と夜の長さがほぼ同じになる日とされています。この日も祖先を敬い、お墓参りをする風習が根付いています。
昔から春分の日には「ぼたもち」、秋分の日には「おはぎ」をお供えしたり食べたりする習慣がありますが、その理由について詳しく見ていきましょう。
季節の花にちなんだ名前の違い
春に咲く牡丹と秋に咲く萩の花にちなんで、春は「ぼたもち」、秋は「おはぎ」と呼ばれるようになったそうです。
そのため、春分の日には「ぼたもち」、秋分の日には「おはぎ」を食べる習慣が広まったといわれています。
小豆の収穫時期と保存状態の違い
昔は冷蔵技術がなかったため、春と秋では小豆の状態が異なりました。
春(春分の時期)は、前年の秋に収穫した小豆を保存していたため、皮が固くなりやすく、裏ごしして「こしあんのぼたもち」にすることが一般的でした。
一方、秋(秋分の時期)は、その年に収穫した新豆の小豆が手に入る時期で皮が柔らかいため、粒あんの「おはぎ」に適しているといわれています。
このように、小豆の状態が異なることから、春分の日には「こしあんのぼたもち」、秋分の日には「粒あんのおはぎ」が食べられるようになったと考えられています。
子どもに春分の日を簡単に伝える方法
春分の日について子どもたちにわかりやすく伝える方法を紹介します。
春分の日はね、この日からお昼の時間がどんどん長くなって、ポカポカあたたかくなるといわれているんだよ!
それにね、春分の日は『お彼岸(ひがん)』っていって、天国にいるおじいちゃんやおばあちゃんに『ありがとう』を伝える日なんだ。だから、お墓参りに行く日でもあるよ。
それからね、春分の日は『自然を大切にする日』でもあるよ。春になるとあたたかくなるから、いろいろなお花や生き物を見ることができて楽しみだよね。みんな元気に過ごしてねっていう気持ちを大切にしようね。
子どもと楽しく春分の日を過ごすアイデア
春分の日にあわせて、子どもと楽しい時間を過ごせるとよいですね。
活動アイデアの例を紹介します。
春探しに出かけよう
春分の日を迎えると、少しずつ暖かくなり、春の訪れを感じられるようになるでしょう。
近所を散歩したり、公園を歩いたりしながら、「どんな春が見つかるかな?」と声をかけると、子どもも楽しみながら自然に目を向けることができそうです。
【春探しのポイント】
- つくしやたんぽぽなど、春の草花を探してみる
- 木の枝を見上げ、冬にはなかったつぼみの膨らみを探してみる
- ちょうちょやありなど、春に出てくる生き物を見つける
子どもたちが主体的に春を探せるように「どんなお花があるかな?」「この虫の名前は知っているかな?」などと問いかけながら、いっしょに歩いてみるとよいですね。
また、保育園では朝の会で「春探しの発表」の場を設け、見つけたものを発表したり、気づいたことを共有したりすると、春の訪れにより興味を持ってもらえそうです。
春分の日にちなんだ活動を考える新卒の保育士さんも参考にしてみてくださいね。
春の歌や手遊びを楽しむ
春の歌や手遊びを保育に取り入れて、季節の移り変わりを感じてみましょう。
「つくしのぼうや」
シンプルな振付で覚えやすい春の手遊びです。
「つくし」を見たことがない子もいるかもしれないので、実物を紹介してから手遊びをすると関心を持ってもらえそうですね。
「春が来た」
昔から親しまれている春の定番ソング。
振り付けを取り入れて、こどもと楽しく歌ってみてくださいね。
「はるですねはるですよ」
動物が登場するかわいらしい歌。
ゆったりしたメロディーなので、リズムに合わせて簡単な振りつけを楽しめそうです。
春分の日がどんな日であるかを知り、子どもたちと楽しい時間を過ごそう
春分の日は、昼と夜の長さがほぼ同じになる日であり、自然に感謝し、ご先祖さまを思う日でもあります。
子どもたちに春分の日に関心を持ってもらえるよう、わかりやすい言葉でどんな日であるかを伝えられるとよいでしょう。
また、春の訪れを感じながら、子どもたちといっしょに自然にふれたり、歌を歌ったりして素敵な時間を過ごせるとよいですね。
なお、「保育士バンク!新卒」では、保育学生さんや新卒の保育士さん向けに遊びネタや実習に役立つ情報などを配信しています。
また、就活・転職のサポートも実施しているので「新卒だけれど、今の園の人間関係に不安があるから、違う園で働きたい」などといったお悩みがありましたら、一度ご相談ください!
あなたらしく働ける職場をいっしょに探していきましょう。