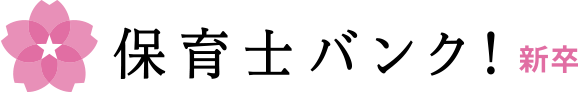保育園に通い始める際に設ける「慣らし保育」の期間。新しい生活がスタートし、不安を抱く子どもや保護者の方がいるかもしれません。今回は、慣らし保育期間の基本的なスケジュールや、ケース別の子ども・保護者の方への対応ポイントを紹介します。また、保育士さんが悩んだときに心がラクになるヒントもまとめたので、参考にしてみてくださいね。
 Paylessimages / stock.adobe.com
Paylessimages / stock.adobe.com
慣らし保育とは
慣らし保育とは、新しい環境に子どもが少しずつ慣れていけるよう、段階を踏みながら保育園生活を始める期間です。
新しい「環境」「先生」「集団生活」と、子どもや保護者の方にとっては初めてのことばかりの毎日。
慣らし保育を通して、少しずつ「保育園が安心できる場所」だと感じてもらえることが大切です。
とはいえ、毎日子どもが泣いていたり、食事やお昼寝が思うように進まなかったりすると、現場の保育士さんは戸惑いや不安を抱える場面があるかもしれません。
などと感じながら過ごす日々に戸惑うことがありそうです。
慣らし保育の期間を乗り切り、子どもたちの園生活を支えられるように、基本的なスケジュールや進め方、対応ポイントまで、詳しく紹介します。新人の保育士さんも参考にしてみてくださいね。
慣らし保育の基本的なスケジュール
慣らし保育の進め方は園によってさまざまですが、一般的には1〜2週間ほどかけて、少しずつ登園時間を延ばしていくケースが多く見られます。
子どもの様子や保護者の方のお仕事の都合に合わせて、保育時間を短縮したり延長したりすることもあり、各家庭に応じた調整が求められるでしょう。
ここでは一例として、1歳児の慣らし保育スケジュールを紹介します。
| 期間の目安 | 保育時間 | 登園時間帯 | 主な活動内容 |
|---|---|---|---|
| 1日目 | 約1時間 | 登園〜9:30頃 |
|
| 2〜3日目 | 約2時間 | 登園〜10:30頃 |
|
| 4〜6日目 | 約4時間 | 登園〜12:30頃 |
|
| 7〜9日目 | 約6時間 | 登園〜14:30頃 |
|
| 10日目以降 | 通常保育 | 園の登園時間に合わせて |
|
子どもが体調を崩して休んだ場合は、状況に応じて初日からやり直すことがあるようです。保護者の方とこまめに連携を図りながら、慣らし保育を進め方を見直せるとよいですね。
【体験談】慣らし保育の子どもへの対応ポイント

慣らし保育の期間中、子どもたちが新しい環境に慣れるために、保育士としてどのように対応すればよいのか悩むこともあるでしょう。
保育士さんの体験談を交えながら、ケース別に子どもへの対応ポイントをまとめました。
ケース1「子どもが泣き止まない」
<対応ポイント>
子どもが泣いているときは、無理に泣き止ませようとせず、まずは「さみしいんだね」「大丈夫だよ」などと声をかけ、気持ちに寄り添う姿勢を大切にしましょう。
抱っこや声かけが逆効果になる場合があるため、子どもの様子を見ながら距離の取り方を工夫することがポイントです。
「泣いている=うまくいっていない」わけではなく、泣くことで感情を表現していると受け止め、焦らずに信頼関係を築けるとよいですね。
他の子の対応も重なる中で思うように関われない日があっても、自分を責めず「今日はそばにいて関わろうと努力した」と自分自身を褒めることも、心の余裕につながりそうです。
ケース2「ご飯を食べない」
<対応ポイント>
慣れない環境の中で食事をすることに、緊張や不安を感じる子もいるでしょう。
まずは「安心してテーブルにつけること」「ご飯の時間を心地よく過ごせること」に目を向けるとよさそうです。
好きなメニューや食べられそうな量を保護者と共有し、負担にならない形でサポートしていけるとよいですね。
「今日の給食おいしそうだね」「一緒にご飯を食べれてうれしいね」などと声をかけながら、給食の時間が楽しいと思ってもらえるように見守っていきましょう。
ケース3「ひとりで過ごしている」
<対応ポイント>
集団に入らず、ひとりで過ごす子の姿を見て「馴染めていないのは、私の関わり方に問題があるのかもしれない」と不安になることもあるかもしれません。
しかし、それはあくまで保育士側からの視点であり、子どもにとっては“安心できる過ごし方”を選んでいる場合もあるでしょう。
自分のペースで少しずつ環境に慣れようとしている過程と捉え、その子のペースを尊重しながら見守っていけるとよいですね。
「楽しそうだね」「〇〇の遊びが好きなんだね」などと、子どもが興味のあることに対して、声かけを意識して、少しずつ信頼関係を築いていきましょう。
無理に集団に馴染ませようとするのではなく、まずは「保育園で安心して過ごせること」を大切にし、子どもの心に寄り添ったうえで、各活動の楽しさを伝えていけるとよさそうです。
【体験談】慣らし保育の保護者への対応ポイント
慣らし保育の期間中は、子どもだけでなく保護者の方も不安を抱えている場合があるでしょう。
ここからは保護者対応で悩みやすいケースや、気持ちに寄り添いながら信頼関係を築くためのヒントをご紹介します。
ケース1「登園時に子どもと離れられない保護者」
<対応ポイント>
慣らし保育の登園時は、子どもだけでなく保護者の方にとっても大きな一歩です。
これまで家庭でずっと一緒に過ごしていた子と離れることに、戸惑う方もいるでしょう。
泣く子どもを前に「保育園に通うのは早すぎたのかな」と悩み、不安な気持ちが溢れてしまう方がいるかもしれません。
そんなときは、「その気持ち、よくわかります」「これから一緒に見守っていきましょう!できる限りサポートします」などと寄り添うことが大切です。
保育士が落ち着いて気持ちを受け止めることで、保護者の方も少しずつ子どもと離れられるようになるかもしれません。
また、お見送りでは「あとで様子をお伝えしますね」などと見通しを持てる言葉も伝えられるとよいですね。
ケース2「子どもが保育園に通うのが”かわいそう”と感じてしまう保護者」
<対応ポイント>
保護者の方の中には、子どもを預けることに後ろめたさや罪悪感を抱えている方もいるかもしれません。
“かわいそう”という言葉には、子どもへの愛情や葛藤、さまざまな感情が込められていることもあります。
そんなときは「たくさん悩まれて、この保育園に通うことを決めてくれたんですね」と、まずは気持ちを受け止める声かけを意識するとよさそうです。
「〇〇ちゃん、少しずつ園に慣れて、昨日は笑顔を見せてくれました」など、子どもの前向きな変化を伝えると、保護者の方が安心してくれるかもしれません。
“かわいそう”ではなく、“子どもの成長を感じられる場が増えた”という気持ちを抱いてもらえるよう、少しずつ園生活に慣れてもらえるとよいですね。
ケース3「何度も様子を確認される保護者」
<対応ポイント>
子どものことが気になり、何度も様子を確認する保護者の方もいるでしょう。「泣いていないかな」「ちゃんとご飯は食べられているかな」と、一日中、心配して過ごしていることがありそうです。
そんなときは、「気にかけてくださってありがとうございます」などと、まずは寄り添う言葉を伝えると安心してもらえるでしょう。
「今日はカスタネットを鳴らして、音遊びを楽しんでいましたよ」「ポテトが好きなんですね!ニコニコしながら食べていました」などと具体的に様子を伝えることで、保護者の方の不安を軽減できそうです。
やりとりを重ねるうちに、「先生たちに任せているから安心できる」と感じてもらえれば、保護者の方も少しずつ安心し、確認の頻度が減っていくかもしれません。
慣らし保育で悩んだときに乗り切るコツ
慣らし保育期間に不安を感じたり、気持ちが沈んだりする保育士さんはいませんか。
最後に、悩んだときに少し気持ちが軽くなるようなヒントをまとめました。
思い通りにいかない日があっても自分を責めない
子どもが泣き続けたり、なかなか保育室に入れなかったりする姿を見ると、焦ってしまうことがあるでしょう。
「今日は子どもと目が合った」「抱っこするとうれしそうにしていた」など、小さな変化に目を向けることが大切です。
完璧な関わりを目指すのではなく、今できることを積み重ねていく姿勢が、信頼関係を築く土台になりそうです。
思い通りにいかない日があっても、できなかったことばかりにとらわれず、自分自身が「できたこと」にも目を向け、自分を責めすぎないようにしましょう。
自分の心を整える時間を大切にする
慣らし保育の期間は、気を張る場面が多く、気づかないうちに心や身体が疲れていることもあるでしょう。
「新しい子どもたちとの関わり」「保護者との信頼づくり」「クラスの雰囲気づくり」など、気を配る日々が続きそうです。
休憩中に深呼吸をしたり、同僚と何気ない会話を楽しんだりと、短い時間でも気分を切り替えられるような過ごし方を意識できると、心が整いやすいでしょう。
無理に頑張りすぎず、自分自身も大切にしながら過ごすことで、気持ちに余裕が生まれ、子どもや保護者の方と丁寧に向き合えるかもしれません。
慣らし保育は大切な時間!悩みすぎずに丁寧な関わりを心がけよう
慣らし保育は、子どもや保護者にとって新しい環境に慣れていくための時間であり、保育士にとっても信頼関係を築く準備期間といえます。
子どもや保護者への丁寧な関わりの積み重ねが、これからの園生活を支える土台になっていくでしょう。
慣らし保育の一日一日を大切に過ごし、進め方を考えたうえで充実した園生活へとつながるよう、しっかりサポートできるとよいですね。
なお、保育士バンク!新卒では、日々の遊びネタや行事のヒントなど、現場で役立つ情報を配信しています。
転職や就職のサポートも実施しているので「働き方を見直したい」「小規模保育園で乳児クラスを担当してみたい」などといった希望がありましたら、ご相談ください。
あなたらしく働ける職場を一緒に探していきましょう。