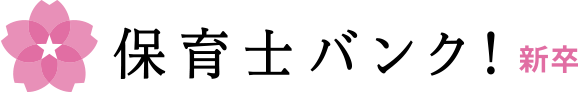保育園で子どもが情緒不安定になったとき、保育士さんはどのように関わればよいのでしょうか。生活環境の変化や2歳児のイヤイヤ期など、子どもの情緒の変化にはさまざまな背景があるようです。今回は具体例を交えて、子どもが情緒不安定になったときの保育士さんの対応や保護者の方への関わり方のヒントをまとめました。

保育園で子どもが情緒不安定になったときの対応を知ろう
保育園では、子どもが突然泣き出したり、不機嫌になったりすることがあるかもしれません。
子どもが情緒不安定になる背景には、生活の変化や家庭での出来事、発達に伴う心の成長などが関係している場合もあるようです。
保育士さんは子どもの気持ちに寄り添いながら、落ち着いて過ごせるように関わっていくことが大切です。
とはいえ、「どんな風に接すればいいの?」「関わり方を間違って、『登園したくない!』と言われたらどうしよう…….」と悩む保育士さんもいるかもしれません。
子どもの様子や状況によって対応は異なりますが、関わり方のヒントをチェックして、日々の保育に役立てていきましょう。
【ケース別】保育園で子どもが情緒不安定になったときの原因と対応方法

まずは、子どもはどのようなときに情緒不安定になるのか、具体例と対応方法を紹介します。
保育園の方針によっても関わり方は異なるため、参考程度に確認してみてくださいね。
入園による生活の変化
入園当初は環境の変化により、不安定な様子が見られることがあるでしょう。
保護者の方との別れや慣れない集団生活への戸惑いが、情緒面に表れるのかもしれません。
特に乳児クラスでは、家庭以外の場所で長時間過ごすのが初めてという子も多く、泣いたり集団の活動に参加できなかったりとさまざまな様子が見られるようです。
具体例
対応方法
まずは無理に活動へ誘わず、その子が落ち着いて過ごせるような関わりを心がけるとよいでしょう。
特定の保育士が一定期間関わり続けることで信頼関係を築き、「〇〇先生がいると安心」と感じられるような関わりを意識するとよさそうです。
好きな絵本やおもちゃを使ったやり取りを繰り返すと、少しずつ表情がゆるんでくることもあるかもしれません。
また、休み明けは保護者の方と離れるのが寂しくて、情緒不安定になる子も多いようです。
そんなときは「うんうん。寂しいよね」と子どもの気持ちに寄り添いながら、「先生と一緒に〇〇しよう♪楽しもうね」などと伝え、さりげなく気持ちを切り替えられる声かけを意識してみましょう。
2歳児のイヤイヤ期
2歳児ごろは、自分の気持ちを少しずつ表現し始める時期です。思い通りにいかなかったりうまく伝えられなかったりすると「イヤ!」という言葉で気持ちを表すことがあるでしょう。
「自分でやりたいけれど、うまくできない」といった気持ちから、順番を待てなかったり泣き続けたりと不安定な場面が見られ、対応方法に悩むことがありそうです。
具体例
対応方法
イヤイヤ期の対応では、まず「気持ちをわかってくれる大人が近くにいる」と子どもが感じられるような声かけが大切です。
「イヤだったんだね」「自分でやりたかったんだよね」と、子どもの気持ちを代弁するように伝えると、安心した表情が見られることもあるでしょう。
また、子どもに「これとこれ、どっちがいい?」と選択肢を示すことで、自分の気持ちを伝えやすくなるかもしれません。
たとえば、「先に靴下を履く?ズボンがいいかな?」「今□□君が遊んでいるおもちゃを使いたかったんだね。他にも△△と〇〇もあるよ」といった声かけを通して、自分で選ぶ機会をつくってみましょう。
子ども自身が「〇〇にする」と意思を伝えられる経験が、気持ちの切り替えにつながることもあるようです。
やり取りがうまくいかない日もあるかもしれませんが、子どもの気持ちを受け止めながら、少しずつその子に合った関わり方を探っていけるとよさそうです。
家庭環境の変化
家庭環境の変化によって、保育園で落ち着かない様子が見られる子どももいるようです。
たとえば、下の子が生まれたばかりのタイミングや引っ越しなど、環境が大きく変わったときは不安を感じることもあるかもしれません。
理由をうまく言葉で伝えられない年齢の場合、「甘える」「泣く」「怒る」といった様子が多く見られ、戸惑うことがあるでしょう。
具体例
対応方法
子どもの行動の変化があったときには、「どうしたのかな?」「何かあったのかな?」と気づく保育士さんの視点はとても大切です。
すぐに理由がわからないこともありますが、「安心したい」「甘えたい」といった気持ちが背景にあるのかもしれません。
たとえば、下の子が生まれたことで落ち着かない様子が見られる場合には、「ママを独り占めできなくて寂しいのかな」と想像しながら、「今日は先生と絵本読もうね」「〇〇ちゃん、大好きだよ」などの声かけを通して、子どもが安心できる関わりを意識してみましょう。
「先生といるとうれしい」「甘えていいんだ」と感じられる関わりが、心の安定につながりそうです。
その子の気持ちの背景に目を向けながら、信頼関係を築いていけるとよいですね。
保育園で子どもが情緒不安定になったときの保護者の方への対応

子どもの情緒に変化が表れたとき、「園ではこんな様子だったけれど、家庭ではどのような様子ですか?」と問いかけ、情報を共有することが大切です。
質問の言い方によっては、「うちの子、大丈夫でしょうか?」「迷惑をかけていませんか?」と心配する保護者の方もいるでしょう。
ここからは、保護者の方への心に寄り添った関わり方のヒントを紹介します。
何気ない会話の中で家庭での様子を聞く
園で子どもに気になる様子が見られたとき、日常の会話の中で家庭での様子を聞いてみることで、行動の背景が見えてくる場合もあるでしょう。
「何かありましたか?」といったストレートな問いかけでは、保護者の方が構えてしまうこともあるかもしれません。
「〇〇ちゃん、最近お昼寝のときに少し泣いていて…」など、園での様子を具体的に伝えながらお話をうかがうと、自然なやり取りにつながるでしょう。
保護者の方の気持ちを受け止める姿勢を大切にする
子どもの様子を伝えたとき、保護者の方が「うちの子だけですか?」「家でもわがままで…」と不安を口にすることもあるかもしれません。
そんなときはすぐにアドバイスをせず、「そうなんですね」「それは心配になりますよね」と気持ちに寄り添う返答を意識するとよいでしょう。
安心して話せる雰囲気をつくると、保護者の方からも「実は…」と家庭での様子を伝えてくれることがあるようです。
まずは、「先生が気にかけてくれている」と思ってもらえるような関わりを心がけたいですね。
ゆっくり話せる時間をつくる工夫をする
保育園の送迎時は慌ただしく、保護者の方と十分に話す時間が取れないこともあります。
気になることがあるときは、「少しだけお時間いいですか?」とあらかじめ声をかけ、個別に話す機会をつくるのもひとつの方法です。
ほんの数分でも落ち着いた雰囲気で会話ができると、保護者の方が本音を伝えてくれることもあるかもしれません。
また、連絡帳に「気になることがあれば、お迎えの際に少しお話しさせてくださいね」と一言添えるなど、無理のない形でつながりを保つ工夫もできるとよいですね。
子どもの様子を一緒に見守っていく姿勢を伝える
子どもの情緒に変化があると、つい「何か問題があるのでは…」と心配になってしまうことがあります。
ただし、保育園での様子を伝えるときは、困った行動だけに注目せず、その子らしい姿や前向きな変化にも目を向けましょう。
たとえば、「泣く時間が少し短くなってきましたよ」「自分からおもちゃに手を伸ばしていました」など、子どもの変化や成長を伝えることで、保護者の方も安心できるかもしれません。
また、「どの子も個性やペースに違いがあるので、ゆっくり見守っていきましょうね」と伝え、サポートする姿勢を伝えられるとよいですね。
また、年度初めの慣らし保育の対応で悩む保育士さんはこちらの記事をみてくださいね。子どもや保護者への関わり方のヒントを紹介しています。
保育園で子どもが情緒不安定になったときは丁寧に関わろう
保育園で子どもに不安定な様子が見られるとき、その背景には生活の変化や心の成長、家庭での出来事など、さまざまな理由があるのかもしれません。
子どもの気持ちに寄り添いながら丁寧に関わっていくことで、少しずつ安心できる時間が増えていくこともあるでしょう。
また、保護者の方とのやり取りを通してお互いの気持ちを伝え合い、子どもの成長を一緒に見守っていける関係が築けるとよいですね。
なお、「保育士バンク!新卒」では、季節の製作アイデアや保護者の方への対応のヒントなど、日々の保育に役立つ情報を配信しています。
就職・転職のサポートも行っているので「もっと子ども一人ひとりと丁寧に関われる園で働きたい」などの思いがある方は、お気軽にご相談ください。
あなたが保育士としてやりがいを抱いて働ける職場を一緒に探していきましょう。