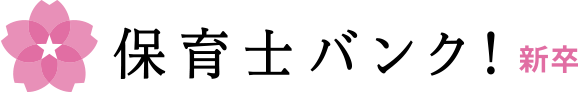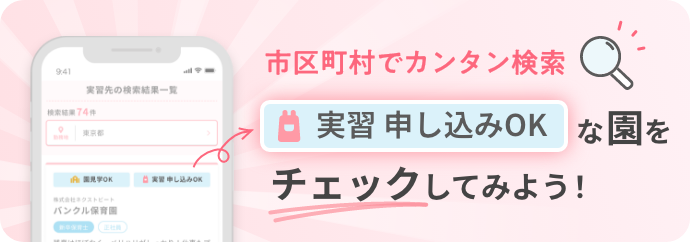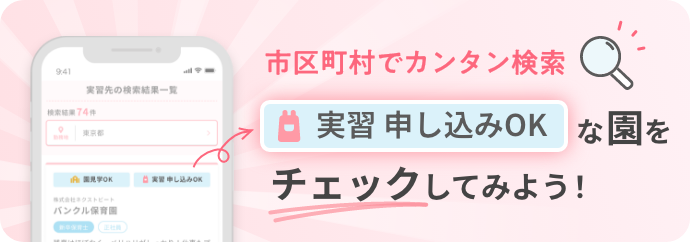保育実習では毎日の目標を立てますが、学びたいことが漠然としており、文章に悩む学生さんも多いはず。今回は、保育実習の目標の書き方を0・1・2・3・4・5歳児別に解説します。前半~後半まで毎日使えるねらいの例文や自己課題なども紹介するので、責任実習や部分実習の目標を立てるときも参考にしてくださいね。「最終日の目標が思いつかない」という方にも必見です!
 milatas / stock.adobe.com
milatas / stock.adobe.com
保育実習の目標を立てるときはどんなことが大切?
保育実習では、実習全体の課題や1日ごとのねらいなど、目標を立てる場面がたくさんあります。
しかし、実習日誌への書き方に悩んでしまう保育学生さんも多いでしょう。
保育実習に参加する目的を理解する
なぜ保育実習を行なうのかを理解できれば、目標設定がしやすくなるかもしれません。
目標の立て方や書き方を見ていく前に、まずは保育実習の目的をおさらいしましょう。
保育現場の雰囲気を知る
1つ目の目的は、保育現場の雰囲気を肌で感じることです。
保育実習では、実際の現場で保育士さんがどのように働いているのかを知ることができます。
子どもとのかかわりや教材・行事の準備などさまざまな業務を体験することで、保育士の仕事について理解を深められそうですね。
実践的なスキルを身につける
2つ目の目的は、座学で学んだ知識を実務の中でより深めることです。
保育士として働くうえでは、学校の授業で得た知識を活かすだけではなく、実際に子どもと接するなかで保育スキルを磨くことが大切となるでしょう。
保育実習に参加すれば、座学では得られない実践的な保育知識を身につけることができるかもしれません。
保育士として働くイメージを持つ
3つ目の目的は、どのような保育士になりたいのかといった具体的な目標を見つけ、保育士の仕事への志望度を再認識することです。
保育士さんの援助を近くで見ることで理想の保育士像が明確になったり、子どもとかかわるなかで保育の楽しさややりがいを感じられたりするかもしれません。
ほかにも、保育現場を経験することで「こんな園で働きたい」と就職先のイメージが膨らみそうですね。
保育実習で目標を立てる必要性
保育実習を行なう目的が把握できたところで、次は目標設定をする重要性についてみていきましょう。
自己課題を認識できる
目標を設定することで、自身の現状を把握しやすくなるかもしれません。
そもそも目標を設定するには、自分が現在できること・できないことを洗い出して把握することが大切です。
自己課題をクリアするにはどうすればよいのか分析し、確認したうえで目標の実現に必要なことを言語化しましょう。
振り返りの機会になる
目標を設定すれば、それに対する自己評価を記録して振り返る機会を作ることができます。
1日ごとに自分が達成できていたのかを振り返れば、クリアできなかった部分を記録して次の日の目標として設定することができるでしょう。
学びたいことをクリアにできる
目標を立てることで、自分のなかで学びたいことが明確になるでしょう。
目標を設定せずに実習に参加すると、何を身につけるべきなのか曖昧なまま最終日を迎えるおそれも。
目標を立てれば自分が学びたいことを認識できるので、実習中に保育士さんに質問するなど積極的に行動できるようになるかもしれませんね。
このように、目標設定をするのにはさまざまな意義があります。実習を実りあるものにするためにも、自分自身でしっかり目標を立てていきましょう。
保育実習での目標の書き方のポイント
 Farknot-Architect / stock.adobe.com
Farknot-Architect / stock.adobe.com
目標設定の重要性を理解したうえで、実際に書く準備を進めていきましょう。ここでは書き方のポイントを紹介します。
自身の知識を深めたい部分を考える
実習を通して、これまで学んできた保育知識を深めていけるような目標を考えてみましょう。
例えば2歳児クラスを担当する場合、覚えた手遊びネタを活かして、「積極的に手遊びを行なって2歳児とかかわる」といった目標を設定してみるとよいかもしれません。
実際に子どもの前で手遊びを行なえば、どんなネタが盛り上がるのかを理解できたり、子どもがよろこぶポイントや演じ方のコツについて知識を深めたりできるでしょう。
年齢やクラスの状況を考慮する
担当する子どもの年齢やクラスの状況に応じて目標の内容を考えるとよさそうです。
例えば、0歳児や1歳児クラスで「はさみを使った製作を行ない、援助のしかたを学ぶ」といった目標は難易度が高いでしょう。
初日に子どもやクラスの状況を観察しながら、年齢や発達を踏まえた適切な目標を設定することがポイントです。
目標は具体的にする
毎日の目標を立てるときは、具体的な行動に落とし込んだ内容を考えるとよいでしょう。
例えば、「1歳児クラスの子どもと積極的にかかわる」という目標であれば、以下のように細分化できそうです。
- 歌や手遊びを通してコミュニケーションを取る
- クラス全員とかかわれるよう、均等に遊びに参加する
- それぞれの子どもが好きな遊びを通してかかわる
このように具体化すれば、実習中に意識して行動すべきことをクリアにできるでしょう。また、目標は記録として残るので、最終日の振り返りもしやすくなりそうです。
自己課題に対する改善策を挙げる
実習が始まってしばらくすると、自分の得意・不得意が明確になるでしょう。
そのため、中盤や後半に向けた目標設定では、自己課題を改善するための対策として目標を考えてみるとよいかもしれません。また、自身が実習で学びたいことを明確にすることも大切です。
例えば、戸外遊びのかかわり方がわからない場合は、「戸外遊びにおける保育士さんの言葉がけやかかわりを学ぶ」といった目標にするとよさそうです。
「保育士バンク!新卒」に就活ついて相談してみる
【前半・中盤・後半】保育実習の目標例文
 buritora / stock.adobe.com
buritora / stock.adobe.com
目標の立て方や書き方を踏まえたうえで、ここでは保育実習の目標の例文を紹介します。
実習前や実習初日、中盤、後半とシーン別にまとめました。
実習前
実習が始まる前に立てる、全体を通した目標の例文を紹介します。
目標例1.「保育士として求められることの基礎を学ぶ」
保育知識や子どもとのかかわり方など、保育士に求められる基礎的なスキルを身につけるという目標です。
- 保育士さんの動きを観察する
- 基本的な保育知識を実践して自分のものにする
以上のポイントを意識すれば、保育現場で役立つ実践的なスキルを身につけられるかもしれませんね。
具体例2.「自分が保育士として成長するための課題を明確にする」
実習では保育スキルを身につけるだけでなく、自分の課題を認識することも大切です。
- 複数の子どもとかかわって、クラスをまとめる保育士さんの様子を把握する
- 保育業務以外の保育士さんの動き方を観察する
以上のポイントを意識して、仕事への理解を深めたり自分の足りない点をクリアにしたりしていきましょう。
具体例3.「理想とする保育士像を見つける」
実習を通して子どもたちと接するうちに、なりたい保育士像がクリアになるかもしれません。
また、保育士さんそれぞれの援助の違いや言葉がけの工夫などを知るうちに、保育観なども明確になるでしょう。
実習前半
実習初日や序盤に立てたい目標の例文を紹介します。
目標例1.「子どもと積極的にかかわる」
実習初日やはじめの数日は、子どもの名前や特徴を覚えるためにも積極的に遊ぶことが大切です。「クラス全員と1回ずつコミュニケーションをとる」のような目標を立ててもよいでしょう。
実習後半に向けて、子どもの好きな遊びや大まかな性格などを早い段階で把握できるとよいですね。
目標例2.「1日の流れを把握する」
保育実習をするうえで、保育園での1日の流れを知ることも重要です。
一般的に遊びや給食の時間は毎日決まっているため、実習前半に把握しておけば子どもへの声かけがしやすくなりそうですね。
目標例3.「保育士さんの働きかけの基礎を学ぶ」
保育士さんが子どもと話すときの姿勢や言葉選び、表情など保育をするうえで大切となる働きかけの基礎を観察しましょう。
1対1で話すときと全体に向かって話すときの違いや、遊びのなかでの声かけと子どもを諭すときの話し方など、場面ごとのかかわり方の違いについても見ておくとよいですね。
目標例4.「子どもの成長や発達を理解する」
保育園にはさまざまな子どもがいるので、心身の成長スピードは一人ひとり異なるでしょう。
保育学生さんはそれぞれの子どもに合った声かけや援助ができるように、成長や発達の様子を理解しておいたほうがよいかもしれませんね。
目標例5.「手遊びを通じて子どもと楽しくかかわる」
子どもたちと関係性を作れるよう、いろいろな手遊びでコミュニケーションを取ることを目標にした例文です。
年齢や季節に合った手遊びをたくさん覚えておき、実習先で取り入れられるとよいでしょう。
実習中盤
子どもとのかかわり方の基礎を学び、保育士の仕事に慣れてくる実習中盤の目標例文を紹介します。
目標例1.「子どもの気持ちを汲み取ってかかわる」
子どもは自分の気持ちをうまく言葉で伝えられないことがあるため、保育士さんが思いを汲み取ることが大切です。
子ども同士のケンカの仲裁やトラブルの場面では、保育学生さんが子どもの気持ちを代弁したり引き出したりしながらかかわることを意識してみましょう。
目標例2.「保護者対応の様子を知る」
保育園では、登園・降園の際に保護者と子どもの様子について報告したり、共有したりすることが一般的です。
その際の言葉遣いや接し方を観察することで、保育士さんが日頃から何に気をつけて保護者対応をしているかを知ることができるかもしれません。
目標例3.「保育士さん同士の連携を学ぶ」
保育現場では、職員同士で子どもの様子を共有したり、活動内容や行事について話し合ったりと、常に連携して業務を進めていることが多いでしょう。
保育士さんたちのやり取りを見ておくことで、実習中の職員さんとのコミュニケーションだけでなく、入職後に仕事を進める際にも役立ちそうです。
連携時に気をつけていることがないか、担当の保育士さんに聞いてみるのもよいかもしれませんね。
目標例4.「食事や排泄の援助を丁寧に行なう」
子どもによっては食事や排泄の援助が必要な場合もあるため、保育学生さんは保育士さんの様子を見ながら援助方法を理解していきましょう。
いっしょに食べ物をスプーンですくう、ズボンを一人で履けるように援助するなど、できる場面から少しずつサポートを始められるとよいですね。
目標例5.「子どもの興味や関心に合わせて遊びを提案する」
実習の中盤になると、クラスの子どもたちがどんなことに興味を持っているかが徐々にわかってくるかもしれません。
一人ひとりの関心に沿った遊びに誘ってみて、充実した活動ができるとよいですね。
実習後半
実習後半は、基本的な知識やスキルを身につけ、保育士の仕事への理解も深まっている頃かもしれません。
前半と比べて後半はどんなことを意識して目標設定すればよいのか、例文とともに押さえておきましょう。
目標例1.「遊びが広がる援助を行なう」
実習後半では、保育士さんから学んだことを徐々に自分なりの形で実践できるようになるかもしれません。
子どもの遊びを盛り上げるために保育士さんがどのようにかかわっているか、どのように環境設定を工夫しているかなど、より保育を充実させるためのポイントをきちんと観察しましょう。
目標例2.「保育以外での保育士さんの動きを学ぶ」
実習の後半になると1日の流れに慣れるようになるため、余裕を持って保育士さんの動きを観察できるようになるかもしれません。
保育以外の活動準備や片づけの様子、給食の配膳、午睡中の業務なども細かく見ておくと、保育士の仕事内容についてさらに理解を深められるでしょう。
目標例3.「自分の考えや特技を活かしてかかわる」
これまでの学びを活かしたうえで、自分なりに工夫して子どもとかかわることも保育の仕事をするうえでよい経験になるかもしれません。
部分実習や責任実習の機会があれば、取り入れたい活動を担当の保育士さんに相談してみましょう。
ピアノや工作、折り紙など自分の特技を活かして活動できれば、自信につながりそうですね。
目標例4.「1日の流れに沿い、自ら声かけや援助を行なう」
実習後半になれば、園の1日の流れを大まかに理解できるようになっているでしょう。
「もうすぐご飯だから手を洗おうね」「お昼寝だから着替えようね」など、1日の流れに沿った声かけや援助を積極的に行なえるとよさそうですね。
目標例5.「保護者対応の流れを学ぶ」
保護者対応も大切な保育業務の一つです。
実習生さんが直接対応することは稀かもしれませんが、保育士さんたちがどのようにコミュニケーションを取っているかを観察してみましょう。
【最終日】保育実習の目標例文
実習生にとって、実習最終日は実習期間の成長を振り返る大切な一日でしょう。
しかし、中には実習の締めくくりとして、各自が設定した目標にどのような目標を立てればよいのか悩む方もいるかもしれません。
保育実習の最終日に使える目標例文を紹介します。
実習最終日の目標例文1.子ども一人ひとりの思いに寄り添って関わる
最終日には、子どもたちの興味や個性に合わせて丁寧に関わることを目標にしましょう。
例えば、〇〇ちゃんのブロック遊びに「何を作っているの?」と声をかけたり、△△くんが絵本を読んでいたら「どんなお話?」と寄り添ったりするなど、個々の関心に応じたサポートを行なうとよいでしょう。
実習最終日の目標例文2.子どもの自主性を尊重しながら接する
子どもが主体的に行動できるように接していきましょう。
「〇〇しよう」と遊びに誘うのではなく、「〇〇くんはどんな遊びがしたいかな」と声をかけ、自身が興味のある遊びがどんなどんなものなのかを考えてもらえるように援助できるとよさそうです。
実習最終日の目標例文3.1日の流れを把握し、自分で主体的に動く
最終日は園での一日の流れを把握し、だいたいの業務に慣れているでしょう。
午前中の自由遊びから片づけのタイミング、給食前の準備、午睡後の着替えなど、次に何が必要かを自分で考えながら、行動できるとよいですね。
実習最終日の目標例文4.子どもの感情に寄り添い、安心してもらえるように配慮する
子どもが不安や戸惑いを感じたときに寄り添い、安心してもらえるような声かけをしていきましょう。
子どもが泣いていたら背中をさすったり、抱っこしたりしながら「どうしたのかな?」と優しく声をかけ、気持ちを受け止められるとよいですね。
実習最終日の目標例文5.子どもが手遊びに楽しく参加できるような雰囲気をつくる
最終日に手遊びやペープサートなどを披露する場合もあるでしょう。
身振り手振りを大きくしたり明るい声で話したりしながら、子どもたちが参加しやすい雰囲気をつくれるとよいですね。
【0・1・2・3・4・5歳児別】保育実習の目標例文
 buritora / stock.adobe.com
buritora / stock.adobe.com
次に、担当する子どもの年齢別に保育実習の目標の例文を紹介します。
乳児クラス(0歳児・1歳児・2歳児)
0歳児
- 子どもが安心してすごせるよう、笑顔でかかわる
- 離乳食の介助やミルクのあげ方について知る
- 泣いている理由を汲み取り、子どもの気持ちに寄り添ってかかわる
- 0歳児への言葉かけやかかわり方を学ぶ
0歳児クラスでは、子ども一人ひとりのペースに合わせて、安心して過ごせるような配慮が見られるかもしれません。その際、保育士さんがどのように子どもとかかわっているか観察しておきましょう。
1歳児
- 月齢差や発達の個人差を理解し、それぞれの子どもに合ったかかわりをする
- 遊びのときと午睡のときの環境の違いを理解する
- 人見知りをする子どもも安心できるよう、笑顔で優しい声かけをする
- スプーンやフォークを使おうとする子どもの援助方法を学ぶ
1歳児は月齢による発達差が見られる時期かもしれません。保育士さんがどのように子ども一人ひとりとかかわっているのかしっかり見て学びましょう。
また、子どもが過ごしやすい環境作りのポイントも把握できるとよいですね。
2歳児
- 子どもの伝えたいという思いを汲み取り、代弁しながら話を聞くようにする
- 子どもの複雑な感情を受け止めて、気持ちが落ち着くような声かけをする
- 身の回りのことをやろうとする意欲を引き出すための適切な援助を知る
- おままごとを通して、子どもとのかかわり方を学ぶ
2歳児は、自我や主張が強まる子どもが見られ始める頃かもしれません。
子どもの「自分が」という気持ちに対し、保育士さんがどのように対応しているかを勉強しましょう。
また、イヤイヤ期を迎える子もいるかもしれないので、子どもの興味を惹くコツなどを聞けるとよいですね。
幼児クラス(3歳児・4歳児・5歳児)
3歳児
- 友だちといっしょに遊ぶ楽しさを味わえるよう仲立ちをする
- 集団遊びにおける保育士さんの援助のしかたを学ぶ
- 子どもができることを把握し、必要な場面で適切に援助する
- 子どもの感情を受け止めながら、楽しく遊べるように援助する
3歳児になると、身の回りのことを一通り自分自身でできるようになるかもしれません。
集団生活に慣れてくる時期でもあるため、クラス全員の活動で、保育士さんがどのように声かけしているのかを観察するとよさそうです。
また、3歳児は感情を表に出しやすい年齢と言われているので、保育学生さんは子どもの気持ちに寄り添いつつ、生活や遊びをサポートすることが大切でしょう。
4歳児
- 友だち同士で遊ぶ様子を観察し、トラブルがないよう見守る
- 子どもの遊びを見守り、適切な場面で遊び方のヒントを出して援助する
- 子ども同士の伝え合いを見守り、思いを代弁しながら適切に仲立ちする
- ねらいに対して、保育士さんがどのような工夫を行なっているのかを理解する
4歳児になると子ども同士のかかわりが活発になり、集団遊びを好む姿も見られるでしょう。
集団遊びでは、輪に入れずに困っている子がいたり、意見のぶつかり合いが発生してしまったりすることもあるかもしれません。
保育士さんが仲立ちしている様子を学び、保育学生さん自身も実践してみるとよいでしょう。
5歳児
- 子どもが遊びを工夫して発展させる様子を観察する
- 遊びのなかで友だちと協力したり、話し合ったりするための援助を工夫して行なう
- 子どもが行事に向けて意欲や目標を持てるようなかかわりを学ぶ
- 子どもが主体の遊びに対して、保育士さんがどのような援助を行なっているのかを知る
5歳児になると、自分なりの考えを深めたり友だちと意見を交換しながら遊んだりする子どももいるかもしれません。
また、5歳児クラスでは行事が多い園もあるようなので、行事に向けた援助や指導の工夫について保育士さんに尋ね、自身の知識を深められるとよいでしょう。
2回目の保育実習での目標の立て方
保育実習の回数や期間は学校によって異なり、なかには2回に分けて実施するところもあるようです。
2回目の保育実習には以下のような特徴があるでしょう。
- 1回目とは受け持つ年齢が違う
- 責任実習や部分実習などを行なう場合がある
- 1回目の経験を活かして子どもや保育士さんの動きを観察できる
このような特徴をもとに、2回目の実習における目標設定の例を紹介します。
目標例1.「年齢による保育内容の違いを知る」
2回目の保育実習では、1回目とは異なる年齢のクラスを受け持つことも多いようです。
年齢によって子どもの発達が異なるのはもちろん、活動内容や室内の環境、保育士さんの接し方も大きく変化するでしょう。
2回目の実習では、新しい年齢の子どもとのかかわりや保育士さんの配慮・援助などを学ぶことに重点を置くとよいかもしれませんね。
目標例2.「設定保育での援助のしかたを学ぶ」
部分実習や責任実習を任されることが多い2回目の実習では、入職に向けて保育士さんのかかわり方や子どもの姿をしっかり観察することが大切になるでしょう。
保育士さんが環境設定や導入においてどのような工夫をしているのか、主活動へどのようにつなげているのかなど、こまかなポイントを見ておけるとよいですね。
また、子どもへの声かけの方法についてもくわしく記録に残しておけば、部分実習や責任実習に活かせるかもしれません。
目標例3.「部分実習での気づきや反省を活かして子どもとかかわる」
部分実習を実践してみて気がついたことやうまくいかなかったことを分析し、改善するための手立てを考えてみましょう。
例えば、部分実習で絵本の読み聞かせを行なったものの、物語が長すぎて子どもたちが飽きてしまったことを反省点として挙げるケースを想定します。
その場合、次の部分実習では、「子どもの発達に合わせた絵本を選ぶ」「話す声に抑揚をつけて子どもの興味を惹く」といった具体的な改善策を目標にするとよいかもしれません。
目標例4.「ねらいを持って責任実習に取り組む」
責任実習では実習生さん自身がねらいを考えて一日の流れを計画することとなります。
”子どもにこんな経験をしてほしい”というねらいを意識して、主活動などの内容を考えてみましょう。
目標例5.「行事に向けた保育の流れを知る」
行事が近い時期であれば、上記のような目標を立ててみてもよいかもしれません。
子どもたちの興味を引き出す導入方法や、中期的な活動の流れの計画といった保育の進め方を学ぶよい機会となります。
また、職員同士での話し合いや準備といった裏方の仕事を知ることも貴重な経験になるでしょう。
保育実習目標の例文を参考に自己課題などを考えながら実習を有意義なものにしよう
今回は、保育実習の目標の書き方や立て方、具体的な例文などを紹介しました。
保育実習の目標とは、保育学生さんが学びたいことや身につけたいスキルを明確化したもので、場合によっては毎日設定することもあるようです。
設定することで自分の課題や改善点に気づくことができたり、振り返りがしやすくなったりといった利点があるでしょう。
特に後半や最終日では、学んだことを自分で実践してみたり応用させたりすることを目標にすれば、実践的な知識やスキルが身につき、実りのある保育実習になるかもしれません。
紹介した目標例文や書き方を参考にして、有意義な保育実習にしてみてくださいね。
- 実習が忙しくて就活している時間がない!
- 就職先の園、どんな基準で選べばいいんだろう…
といったお悩みはありませんか?
保育士バンク!新卒では、保育士専門に就職支援を実施しています!
専属のアドバイザーが、求人の紹介から履歴書の添削・面接対策まであなたの就活をフルサポート。
あなたらしく働ける園を保育士バンク!新卒でいっしょに探しましょう♪