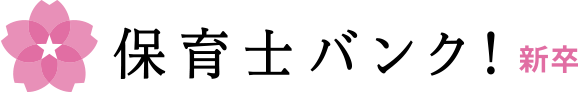保育実習では日記や記録の書き方に悩む保育学生さんも多いでしょう。実習での学びや疑問を書き残すための保育書類ですが、目標や考察、感想などの例文があると書く内容がわかりやすいですよね。今回は、保育実習の日誌や記録の書き方を紹介します。ねらいや実習生の目標の例文、感想や考察のポイントなどくわしくまとめました。

Bacho/shutterstock.com
保育実習日誌を書く目的とねらい
保育実習の日誌や記録とは
保育実習で書く「実習日誌」とは、その日の様子とともに保育者や子どもたちの動きをまとめた記録です。
保育の現場に出ると、なぜその活動をしてどのように進めていくのかを自分で決めていくことになるので、自分自身のための実習記録とも言えるでしょう。
記録方法には2種類がありますが、それぞれの特徴は以下の通りです。
時系列に即した記録
子どもの登園から降園までの時間の流れに沿いながら「環境構成」「子どもの活動」「保育者の援助」「実習生の援助や気づき」などを記入するものです。
時系列に保育の流れを一覧で記入できるという特徴があります。
エピソードを中心とした記録
1日の流れは簡潔に記入し、その日の保育実習で「印象に残ったエピソード」を丁寧に考察していくものです。
保育学生さんが印象に残った出来事を深く分析できるという特徴があります。
保育実習日誌を書く目的・ねらい
日々学んだことを分析する時間を設けることが実習日誌の大きな役割の一つですが、日誌を書くねらいには、以下のような目的があるでしょう。
- 考察と振り返りのため
- 実習指導担当の先生に学びや気づきを伝えるため
- 就活や入職後の参考資料にするため
このように、実習日誌は自分だけでなく、実習指導担当の先生との情報共有やコミュニケーションを密に連携するためのツールとなります。
保育実習日誌や記録を正確に作成し、より実りある実習ができるよう役立てていきましょう。
【項目別】保育実習日誌の書き方
ここでは、保育実習日誌の形式に沿って、項目ごとに書き方や例文を解説していきます。
保育実習日誌のフォーマットは在籍している学校によって異なりますが、おおむね次のような項目があるでしょう。

ここからは、以下の項目にわけてポイントと例文を紹介します。
- 日付・目標
- 保育実習記録欄(活動時間と環境構成、子どもの動き、保育者の援助など)
- 感想・反省・考察
日付・目標の書き方

ポイント1.日付・天候・名前・クラス名・子どもの人数など
季節や天候、担当した子どもの年齢や数で、一日の過ごし方や子どもとの遊び方、学んだことが変わってくるため、活動を振り返る際の重要な情報になります。
ポイント2.実習の目標とねらい
その日の主な活動に対する目標(ねらい)を書きます。
担当する年齢や実習園の保育計画などをもとに、その日取り組みたい内容を2~3ほど挙げましょう。
<例文>
保育実習前半:「子どもたちの名前を覚える」「保育園での1日の流れを把握する」など
保育実習後半:「担任保育者としてのかかわり方を知る」「保育者のかかわりの意図を学ぶなど
保育実習期間の時期によっても、実習生さんの目標やねらいは変わるかもしれません。
一日の実習終了後に、翌日に学びたいことや実践したいことを考えて記入するとよさそうです。
担当クラスにおける長期的な指導計画のねらいについては、実習指導担当の先生に確認して明確にしておくとよいでしょう。
保育実習記録欄の書き方

ポイント1.活動時間と環境構成
時間の欄には、活動が切り替わったときの時刻を記入します。
これによって、活動の準備にどのくらい時間がかかるのかなどがわかるため、部分実習や責任実習で指導計画を立てる際にも役立ちます。
こまめにメモをしておくか、時刻を記憶しておくようにしましょう。
環境構成は、保育室内の構成がどのようになっているか、保育者が活動ごとに環境をどのように変化させているかなどを図や言葉で記入します。
環境図を書く場合は、場所、机や椅子の配置、玩具の置き方などを簡単に書いて、わかりやすく表記することを意識しましょう。
ポイント2.子どもの活動
時系列に沿って、朝の会や遊び、製作、昼食、午睡など子どもの活動内容を記入します。
まずは大きな活動ごとに項目で区切ってまとめ、その中の細かい姿を箇条書きで書いていくとわかりやすいかもしれません。
記入する際のポイントは、以下の例文のように具体的な子どもの姿を書くことと言えます。
<例文>
- 当番の子どもが前に出て朝の挨拶をする。
- 子どもが自分の使う椅子を移動させ、コップと箸、ナフキンを出して食事の準備をする。
- 食事が終わった子どもから、食器などを所定の位置に片付ける。
ここでは、子どもを主語にした文章で記述するのが大切になります。
さらに、活動の中で子どもの様子について気づいたことがあれば、「なかなか準備が進まない子がいる」「苦手な野菜を残す子がいる」などを書き足し、子ども一人ひとりの動きに視点を向けてみるとよいでしょう。
ポイント3.保育者の援助
保育者がどのような動きをしているのかを具体的に学ぶために、子どもへの援助の仕方や内容を記入します。
<例文>
- 担任保育士が大きな袋を出し、「お腹が空いたよ、新聞紙が食べたいよ」と子どもに呼びかけ、片づけを促す。
- 進んで片づけをしていた子どもに「ありがとう」と声をかける。
保育者の援助となる言葉かけや行動は、すべて意図をもって行っていることでしょう。
どのような声かけやかかわりをしていたか、できるだけ細かく書くとよいかもしれません。
また、この欄の文章は、主語を保育者にして表記することに注意しましょう。
<例文>
「保育者にお礼を言われてうれしそうにする」(子どもが主語)
→「子どもがうれしさを味わえるよう保育者がすすんでお礼を言う」(保育者が主語)
記録が書けたら再度文章を読み返してみて、動作の主体が子どもであるか、保育者であるかを今一度確認するとよさそうです。
ポイント4.実習生の援助・気づき
保育実習日誌では、保育者の援助や配慮に対する「実習生の気づき」が大切なポイントになります。
子どもの動きや担任保育士さんのかかわりにどのような発見があったのか、また学生さん自身がしたかかわりの内容を記入しましょう。
<例文>
- 「大きな袋が新聞紙を食べる」という見立てをして、子どもが片づけを楽しめるような工夫をしていた。
- まだ遊びたいという子どもに対し、「見て!〇〇先生が持っているあの袋、お腹が空いているみたいだよ」と興味がもてるような声かけをする。
自ら行動したうえで気づいたことや、保育者の援助から感じたこと、考察などを書きます。
一日の活動のなかでの自分の姿を振り返り、翌日につながるような内容を心がけましょう。
この欄では、主語が実習生になるよう表記することに注意して記入する必要があります。
また、実習生の動きと保育士の動きは同じ欄に書くこともあるので、以下のように記号をつけておくのもよいでしょう。
- 「○」…保育者の動き
- 「●」…実習生の動き
学生さん自身や実習指導担当の先生などが見たとき、どちらの動きか区別しておくことで、見分けがつきやすくなるかもしれません。
感想・反省・考察の書き方

1.感想・反省・考察
感想・反省・考察の欄には、1日の実習を通して、感じたことや反省点を具体的に書きます。
それぞれ、以下のポイントを参考にするとよいでしょう。
- 感想:その日にあったできごとのなかで、特に心に残ったことや疑問に思ったことなどを書きとめます。
うれしかったことや困ったことなどを素直に書きましょう。 - 反省・考察:その日の目標に対して、達成できなかったことやその理由、原因などを考察し、翌日につなげ新たな目標とします。
また、疑問に思ったことも書いておくと、実習指導担当の先生がコメントや回答をしてくれるかもしれません。
以下のように、5W1Hを意識して簡潔に書くようにしましょう。
- 「いつ、どこで」
- 「誰(子どもか先生か)がどんな行動をした結果」
- 「どのような疑問を感じたのか?」
疑問を書くときの注意点は、その時の状況をできるだけ正確かつ具体的に伝えることです。
また、考察や反省の締めくくりは、「もっと〇〇できればよかった」「明日はこうしたい」など、次の日の実習につながる表現で書き終えられるとよいかもしれません。
2.担任指導職員欄
担任指導職員欄には、実習指導担当の先生が保育学生さんの感想や考察を受けての指導やアドバイスなどを書き込みます。
主に、以下のような例が挙げられるでしょう。
- 担当保育者がその日一日実習生と過ごした所感感想欄で実習生が抱いた質問や疑問への回答
- 日誌で挙げた課題に対しての客観的な評価
できている部分と、明日につなげる課題やねらい
返却されたら内容をしっかりと読み込んで、翌日の目標や指導案の立案に反映させていきましょう。
保育実習日誌の書き方のポイント

Antonio Guillem/shutterstock.com
では、実際に保育実習日誌を書くとき、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。書き方の注意点を紹介します。
丁寧に記録する
実習日誌は黒ペン(ボールペン)で手書きし、可能な限り誤字・脱字などの訂正がないように、慎重に書くことが大切です。
園長先生や実習指導担当の先生に読んでもらうものなので、文字は大きさを揃え、丁寧に記入しましょう。
また、日誌内の誤字の訂正方法は園によって方針が異なります。
修正テープを使ってよいか、または二重線を引いて訂正印を押す必要があるかなど、園側に事前確認をするようにしましょう。
メモを活用する
一日分すべての活動や保育士の働きかけ、子どもの様子の細かい部分を記憶することは難しいかもしれません。
そのときは、子どもへどのような声かけをしたかや子どもの面白い発想、喧嘩したときの対応など、自分が得たこと・気づいたことをメモしておくようにしましょう。
ただし、実習中は子どもとの遊びや学びを最優先にすることや、尖ったペン先で子どもを傷つけないといった配慮から、実習中のメモを禁止している方針の園もあるようです。
そういった場合は、できる限り活動中のできごとの時刻をこまめに確認し、記憶しておく必要があります。
休憩時間などに記憶していた内容をメモに書き写すとスムーズですね。
正しい言葉遣いを意識する
実習日誌は正しい言葉遣いで書くことを意識しましょう。
文頭には必ず主語を入れることや、文末を「です・ます調」か「である調」に統一することがポイントになります。
また、「ら抜き言葉」や「い抜き言葉」といった話し言葉を使わないことにも注意が必要です。
加えて、保育実習で作成する日誌・記録や指導案には、保育書類ならではの言い回しや用語を使用することが求められます。
以下の表に、間違えやすい保育の専門用語をまとめました。
| 間違えやすい表現 | 保育書類に書くなら |
|---|---|
| ~させる | ~を促す、~と声をかける ~するよう伝える、~を育む、~を養う |
| 先生 | 保育者 (保育園では保育士、幼稚園では教師、教諭など施設によって使い分ける場合も) |
| 教室 | 保育室 |
| お母さん | 保護者、母親 |
| 登校、下校 | 登園、降園 |
| 昼ごはん | 昼食、給食 |
| お昼寝 | 午睡 |
| おしっこ、うんち | 排泄 |
| お外、お庭 | 戸外、園庭 |
| おもちゃ | 玩具 |
| 制作 | 製作 |
保育実習日誌では、基本的には「お~」「ご~」などの丁寧語を付けないことがポイントになります。
用語の使い方にはいくつかパターンがあるため、園や学校の規定に合わせて活用してみてくださいね。
保育実習日誌の書き方を知って学びを記録に残そう
今回は、保育実習日誌の目的やねらい、書き方の注意点、項目ごとの例文やポイントを紹介しました。
実習日誌の記録につながるよう、実習中には保育者や子どもの動きだけでなく全体を見ることを意識しながら観察するとよさそうです。
新たな気づきがあった場面や感じたことはその場で時刻とともにメモに書き留めておくと、日誌も書きやすくなるかもしれません。
実際に日誌を書くときは、例文やポイントを参考にしながら自分自身の行動を振り返り、入職後にも活かせるような記録が残せるとよいですね。